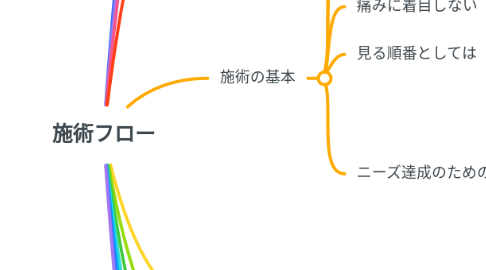
1. 手技
1.1. bilife
1.1.1. 副交感神経の活性
1.2. カイロ
1.2.1. 脊柱のアライメント調整
1.2.1.1. 脊柱に付随する、神経、筋肉の滑走性を改善
1.2.2. モビライゼーション
1.2.2.1. 神経の伝達障害の改善
1.2.3. アジャスト
1.2.3.1. 神経の伝達障害の改善
1.3. 筋肉に対するアプローチ
1.3.1. アナトミートレイン
1.3.1.1. 筋肉、神経の滑走性を改善
1.4. 感覚器に対するアプローチ
1.4.1. 聴覚に対するアプローチ
1.4.1.1. 聴覚に刺激を入れる
1.4.1.1.1. 機能低下の改善
1.4.2. 視覚に対するアプローチ
1.4.2.1. 視覚に刺激を入れる
1.4.2.1.1. 機能低下の改善
1.4.3. 触覚に対するアプローチ
1.4.3.1. 低刺激
1.4.3.1.1. バイブレーション
1.5. 呼吸に対するアプローチ
1.5.1. 胸郭を開きやすくし、呼吸しやすくする
1.6. 流水
1.6.1. 皮膚・筋肉・関節・神経の可動性・滑走性を改善
1.7. 陰圧・生しぼり・厚しぼり
1.7.1. 血流改善
1.8. 内臓調整
1.8.1. 迷走神経の活性、内臓への血流量を増やす
2. 検査
2.1. カイロ
2.1.1. スタティックパルペーション
2.1.2. モーションパルペーション
2.2. 脳機能
2.2.1. 呼吸
2.2.1.1. コントロールポーズ
2.2.2. 自律神経
2.2.2.1. 視覚に対する検査
2.2.2.2. 聴覚に対する検査
2.2.2.3. 各ROM・MMT
2.2.2.3.1. 特に頸椎・足関節
2.2.3. 体性感覚
2.2.3.1. ROM・MMT
2.2.4. 小脳検査
2.2.4.1. 指鼻テスト
2.2.4.2. 回内回外テスト
2.2.4.3. ペダルテスト
2.2.5. 内臓
2.2.5.1. 圧痛・張り
2.2.5.2. 血液検査リーディング
3. 指導
3.1. 食事・栄養療法
3.2. ストレスマネジメント
3.3. 呼吸エクササイズ
3.4. 睡眠療法
4. フロー
4.1. *問診である程度あたりを付ける (すべての検査はできない)
4.2. ビリーフ(副交感神経の活性)
4.2.1. どこの問題?
4.2.1.1. 筋肉・骨格?
4.2.1.1.1. ROM?
4.2.1.1.2. MMT?
4.2.1.1.3. 炎症
4.2.1.2. 脳神経?
4.2.1.2.1. PMRFの異常
4.2.1.2.2. 脊柱のアライメント異常
4.2.1.2.3. 体性感覚の異常
4.2.1.2.4. 自律神経の異常
4.2.1.2.5. 呼吸?
4.2.1.2.6. 内臓問題?
4.2.1.2.7. 血液?
5. 施術の基本
5.1. 患者の主訴と関連が高い悪い部分を見つける
5.1.1. あくまで主訴との関連
5.1.1.1. 完璧を目指さない、ベターを目指す
5.2. 問題点を見つけたら、それの改善に徹する
5.2.1. 施術、セルフケア、自宅でのケアも含めて
5.3. 痛みに着目しない
5.3.1. その場で痛みが変化しなくても、自分の治療計画との結びつきがあればよい
5.3.1.1. *決して楽をしているわけではない
5.4. 見る順番としては
5.4.1. ①ROM②MMT③リスティング(立位、座位)④脳機能⑤血液リーディング
5.5. ニーズ達成のための施術計画書をちゃんと作る
5.5.1. 項目①ゴール設定(終わりの日)
5.5.2. ②適切な通院日
5.5.3. ③状態変化の目安
5.5.3.1. 主訴も大切だが、自分の悪いと思ったところが改善しているかどうか
5.5.4. ④ゴール後に継続通院のお誘い
5.5.4.1. *2:6:2の法則
6. 初診
6.1. 問診
6.1.1. 施術のヒントや状態を把握する
6.1.2. ラポールを構築する
6.2. 検査
6.2.1. 問診を元にMMT、ROM検査をする
6.2.2. パスート・マンテスト
6.2.2.1. (視覚・聴覚検査)
6.3. プレゼン
6.3.1. 結論から話す
6.3.1.1. *相手に自分の原因はなんだと思うかを聞いてみる
6.3.1.1.1. *相手の常識を知る上で必要な質問
6.3.2. *驚きと納得
6.3.2.1. 問題→原因→解決策→未来
6.3.2.2. 常識を壊すストーリーを考えておく
6.3.2.3. *悪い所が複数ある場合は一つに絞って伝える
6.3.3. 施術方法や特徴、時間を話す
6.3.4. 疑問や質問等がないか確認する
6.4. 施術
6.4.1. こまめにビフォーアフターをとる
6.4.1.1. 効果確認と効果実感
6.5. 通院指導
6.5.1. よくなっていく段階をスモールステップで話す
6.5.2. 通院頻度や回数を具体的に話す
6.5.3. 金額を話す
6.5.4. 疑問や質問等がないか確認する
6.5.5. 次回に自律神経を整えるサプリメントの試飲をするか聞く
7. 2診察
7.1. あいさつや表情、所作入ってくるまでの動きをみる
7.2. 問診
7.2.1. 気になったことやいつもと違う症状が無かったか聞く
7.3. *サプリメントを試す
7.4. 施術
7.4.1. なければ施術に入る
7.4.2. あれば話を聞いて目星をつけて、検査して状態を説明し、施術に入る
7.4.3. 施術のビフォーアフターをこまめに取る
7.4.4. 事前に準備していた、またはその時気になった施術中にきいておくことや話しておく事を聞きながら施術する
7.5. 2診察説明・通院指導
7.5.1. 患者さんの望む未来をゴールにおいて、逆算で説明を考えておく
7.5.2. 問題→原因→解決策→未来
8. 3診目
8.1. あいさつや表情、所作入ってくるまでの動きをみる
8.2. 問診
8.2.1. 気になったことやいつもと違う症状が無かったか聞く
8.3. 施術
8.3.1. なければ施術に入る
8.3.2. あれば話を聞いて目星をつけて、検査して状態を説明し、施術に入る
8.3.3. 施術のビフォーアフターをこまめに取る
8.3.4. 事前に準備していた、またはその時気になった施術中にきいておくことや話しておく事を聞きながら施術する
8.4. 通院指導
8.4.1. 今日のまとめを話し、次回治療日程を決めていない人は決める
9. 4診目
9.1. あいさつや表情、所作入ってくるまでの動きをみる
9.2. 問診
9.2.1. 気になったことやいつもと違う症状が無かったか聞く
9.3. 施術
9.3.1. なければ施術に入る
9.3.2. あれば話を聞いて目星をつけて、検査して状態を説明し、施術に入る
9.3.3. 施術のビフォーアフターをこまめに取る
9.3.4. 事前に準備していた、またはその時気になった施術中にきいておくことや話しておく事を聞きながら施術する
9.4. 通院指導
9.4.1. 今日のまとめを話し、次回治療日程を決めていない人は決める
9.4.2. ヒアリングシートを渡す
10. 5診目
10.1. あいさつや表情、所作入ってくるまでの動きをみる
10.2. 問診
10.2.1. 気になったことやいつもと違う症状が無かったか聞く
10.3. 施術
10.3.1. なければ施術に入る
10.3.2. お腹を触ってアフターを一つ取っておく → 次回の食事指導に繋げる為に
10.3.3. あれば話を聞いて目星をつけて、検査して状態を説明し、施術に入る
10.3.4. 施術のビフォーアフターをこまめに取る
10.3.5. 事前に準備していた、またはその時気になった施術中にきいておくことや話しておく事を聞きながら施術する
10.4. 通院指導
10.4.1. 今日のまとめを話し、次回治療日程を決めていない人は決める
10.4.2. ヒアリングシートに答える
11. 6診目
11.1. あいさつや表情、所作入ってくるまでの動きをみる
11.2. 問診
11.2.1. 気になったことやいつもと違う症状が無かったか聞く
11.3. 施術
11.3.1. なければ施術に入る
11.3.2. あれば話を聞いて目星をつけて、検査して状態を説明し、施術に入る
11.3.3. 施術のビフォーアフターをこまめに取る
11.3.4. 食事の話を体の状態と合わせて話をする
11.4. 通院指導
11.4.1. 今日のまとめを話し、次回治療日程を決めていない人は決める
11.4.2. 血液検査と食事のメモを持ってきてもらう
12. 7診目
12.1. あいさつや表情、所作入ってくるまでの動きをみる
12.2. 問診
12.2.1. 貰った血液検査と食事について話をする
12.2.2. 気になったことやいつもと違う症状が無かったか聞く
12.3. 施術
12.3.1. なければ施術に入る
12.3.2. あれば話を聞いて目星をつけて、検査して状態を説明し、施術に入る
12.3.3. 施術のビフォーアフターをこまめに取る
12.3.4. 事前に準備していた、またはその時気になった施術中にきいておくことや話しておく事を聞きながら施術する
12.4. 通院指導
12.4.1. 今日のまとめを話し、次回治療日程を決めていない人は決める
12.4.2. 栄養指導を一つは入れる
12.4.2.1. 患者さんの立場に寄り添って決める
12.4.2.2. *患者さんの生活を聞き、出来そうな範囲で入れていく
12.4.2.3. お腹なら~と入れる内容もあらかじめ決めておく
