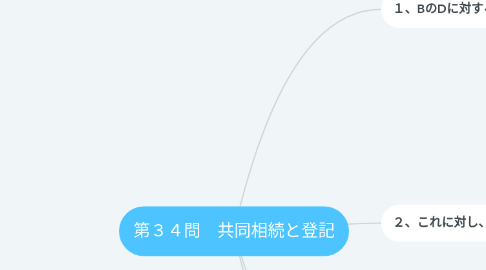
1. 1、BのDに対する、本件不動産所有権(206)に基づく物権的妨害排除請求としてのDの抵当権(369条1項)につき、Bの持分を除外する更生登記手続請求
1.1. ⑴①Bの持分②D抵当権登記
1.2. ⑵要件検討
1.2.1. ア、配偶者Bは相続人なので、Aの死亡で本件不動産を相続(882、896本文)
1.2.1.1. 共同相続の効力として、本件不動産は子Cと共有(249条以下)となる(898)
1.2.1.1.1. (持分は配偶者Bと子Cで各1/2(900条1項))
1.2.2. イ、②も認められる
2. 2、これに対し、Dは相続による共有持分の取得をBは「第三者」Dに対抗できないと主張(177)
2.1. ⑴D主張の通り、相続による持分取得も「不動産に関する物権の得喪及び変更」に含まれる
2.1.1. そして、Bはその登記を具備してない
2.2. ⑵では、Dは「第三者」にあたるか
2.2.1. ア、意義
2.2.1.1. 当事者及び包括承継人以外で登記の欠缺を主張する正当な利益を有する者
2.2.2. イ、Dは相続による持分取得の当事者及び包括承継人ではない
2.2.3. ウ、よって、Dの主張が認められるかはBの登記欠缺を主張する正当な利益の有無にかかる
2.3. ⑶Dの前記正当な利益の有無
2.3.1. ア、Dは共同相続人Cの配偶者EとBの持分について抵当権設定契約をしている
2.3.1.1. しかし、そもそもEはBの持分に関して無権利者
2.3.2. イ、Cを本人とする無権代理行為についてはCの追認(113条1項)を得ている
2.3.2.1. よって、本件抵当権設定登記は共同相続人Cによるものと同視できる
2.3.3. ウ、共同相続人とその持分を超えた部分について契約した相手方は登記の欠缺を主張する正当な利益を有するか
2.3.3.1. (ア)共同相続人と言えども自己の持分超えた部分については無権利者にすぎない
2.3.3.2. そして、各共同相続人は遺産分割手続(906条以下)を経ないかぎり、登記を具備することはできない
2.3.3.2.1. 相続直後に共有の登記を求めるのは不当
2.3.3.3. また、無権利者との契約の相手方は94条2項類推で保護できる
2.3.3.4. よって、正当な利益を認めるべきでない
2.3.3.5. (イ)DはBの登記の欠缺を主張する正当な利益を有さない
2.4. ⑷よって、Dは「第三者」にあたらない
2.4.1. Bは登記なくしてDに自己の持分取得を対抗できる
