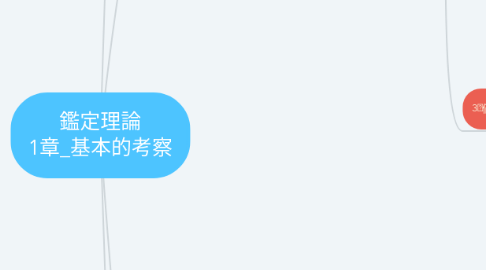
1. 1節_不動産の価格
1.1. 1⃣不動産のあり方
1.1.1. (1)不動産=土地+定着物
1.1.2. (2)土地は「有用性」があるため「基盤」である
1.1.2.1. 「基盤」=すべての国民の生活と活動に欠くことができない基盤
1.1.2.2. 「有用性」=建物を建築する、植物を生育するなど
1.1.3. (3)「土地と人間の関係」は、「不動産のあり方」に現れる
1.1.3.1. 関係=「土地」を「人間」が色々な目的のためにどのような利用をするか
1.1.3.2. 不動産のあり方=「構成」+「貢献」
1.1.4. (4)「不動産のあり方」は
1.1.4.1. ←「4要因の相互作用」で決定される
1.1.4.1.1. 4要因=自然的、社会的、経済的および行政的な要因
1.1.4.2. →経済価値の本質を決定する
1.1.4.3. ←「価格」を選択指標に決定される
1.1.4.3.1. 価格=不動産の経済価値を具体的に表すもの
1.2. 2⃣不動産の価格
1.2.1. (1)「価格」=「不動産の経済価値」を貨幣額で表示したもの
1.2.1.1. ①われわれが認める効用
1.2.1.2. ②相対的希少性
1.2.1.3. ③有効需要
1.2.1.4. の三者の相関結合によって生ずる「不動産の経済価値」
1.2.2. (2)「不動産の経済価値」は「4要因の相互作用」によって決定される
1.2.2.1. 4要因は上記三者を動かす
1.2.3. (3)「価格」と「4要因」の関係性
1.2.3.1. 「価格」が「要因」の影響下にある
1.2.3.2. 「価格」が選択指標として「要因」に影響を与える
2. 2節_不動産と価格の特徴
2.1. 1⃣土地の特性
2.1.1. 導入:「貢献」は「価格」として現れる。
2.1.1.1. 「土地」は「次の特性」を持っている
2.1.2. (1)自然的特性
2.1.2.1. 動かない
2.1.2.1.1. ①地理的位置の固定性
2.1.2.1.2. ②不動性(非移動性)
2.1.2.2. 変わらない
2.1.2.2.1. ③永続性(不変性)
2.1.2.2.2. ④不増性
2.1.2.3. 唯一無二
2.1.2.3.1. ⑤個別性(非同質性、非代替性)
2.1.2.4. まとめ:固定的であって硬直的
2.1.3. (2)人文的特性
2.1.3.1. いろんな使い方
2.1.3.1.1. ①用途の多様性(用途の競合、転換及び併存の可能性)
2.1.3.2. くっついたり、わかれたり
2.1.3.2.1. ②併合及び分割の可能性
2.1.3.3. 変わっていく
2.1.3.3.1. ③社会的及び経済的位置の可変性
2.1.3.4. まとめ:可変的であって伸縮的
2.1.4. まとめ:
2.1.4.1. 「不動産」は「特性条件」を前提として利用され、「有用性」を発揮する
2.1.4.1.1. 与えられた手札で勝負する
2.1.4.2. 「条件の変化」に伴って、「利用形態」+「有用性」は変化する
2.1.4.2.1. 軍艦島は、炭鉱→最前線→観光地
2.2. 2⃣地域の特性
2.2.1. (1)不動産の地域性
2.2.1.1. 不動産は
2.2.1.1.1. ①「条件共通」によって「他の不動産」と「地域」を構成
2.2.1.1.2. ②「地域の構成分子」として
2.2.1.1.3. ③「関係」を通じて「有用性」を発揮する
2.2.2. (2)地域の特性
2.2.2.1. 地域には
2.2.2.1.1. ①「機能等」に従って「各種」が認められる
2.2.2.1.2. ②「個別の不動産」と同様に
2.2.2.1.3. ③相互関係を通じ、「位置」を占める
2.3. 3⃣価格の特性
2.3.1. 導入:「不動産の特徴」により「不動産の価格」も「次の特徴」を指摘可
2.3.2. (1)正の相関関係
2.3.2.1. ①「不動産の経済価値」は
2.3.2.1.1. 交換の対価=価格
2.3.2.1.2. 用益の対価=賃料
2.3.2.2. ②「価格と賃料」は「元本・果実の相関関係」がある
2.3.2.2.1. 価格と賃料があって相関しているよ
2.3.3. (2)権利の対価
2.3.3.1. ①「価格等」は「権利の対価」であり
2.3.3.2. ②「二の権利」が「一の不動産」にある場合
2.3.3.2.1. 「それぞれの権利」に「価格等」が形成されうる
2.3.4. (3)長期・変化
2.3.4.1. ①「地域」は「固定」ではなく「変化」である
2.3.4.1.1. 地域が変わるんだから
2.3.4.2. ②「利用形態」が
2.3.4.2.1. 「最適」かどうか
2.3.4.2.2. 現在「最適」でも、持続できるか
2.3.4.2.3. 常に検討が必要
2.3.4.3. ③「価格」は「長期考慮」に形成
2.3.4.3.1. 「今日の価格」は
2.3.5. (4)個別事情性
2.3.5.1. ①「現実価格」は
2.3.5.1.1. 「個別的に形成」
2.3.5.1.2. 「個別的事情」に左右されがちなもの
2.3.5.2. ②「適正価格」は「一般人には困難」
2.3.5.3. ③「適正価格」は「鑑定評価」が必要
2.3.5.3.1. 一般人にはできないから鑑定士が必要
3. 3節_不動産の鑑定評価
3.1. 1⃣イントロ
3.1.1. (1)「不動産適正価格の算出」には「鑑定評価活動」に依存せざるを得ない
3.1.1.1. 難しい不動産には評価が必須
3.1.2. (2)「鑑定評価」は「経済価値」を判定し、「貨幣額」で表示すること
3.1.2.1. 鑑定とは、経済価値を円にすること
3.2. 2⃣形式的要件
3.2.1. 「秩序の中」で「価格/賃料」が「どこに位置するか」を指摘すること
3.2.1.1. 位置づけを指摘すること
3.2.2. (1)「対象の的確認識」のうえに
3.2.2.1. ターゲット
3.2.3. (2)「資料」を収集/整理
3.2.3.1. データ
3.2.4. (3)「価格形成要因」「諸原則」の十分な理解
3.2.4.1. 前提知識
3.2.5. (4)「手法」を駆使し
3.2.5.1. 計算
3.2.6. (5)「資料」を分析し、「要因」を判断
3.2.6.1. 検討
3.2.7. (6)「最終判断」に到達し、「貨幣額」をもって表示
3.2.7.1. 結論
3.3. 3⃣実質的要件
3.3.1. (1)判断の当否
3.3.1.1. ①「鑑定士の能力」の如何+「能力行使の誠実さ」の如何にかかるもの
3.3.1.1.1. できる人が真面目にやるかどうか
3.3.1.2. ②「資料収集整理の適否」+「分析解釈の練度」に依存する
3.3.1.2.1. データと経験に依存
3.3.2. (2)正しさの前提
3.3.2.1. ①「知識・経験・判断力」を持ち
3.3.2.2. ②「発揮できる専門家」によってなされるとき
3.3.2.3. ③「合理的・客観的に論証」となる
3.3.2.3.1. 能力があって、発揮できる人がやって初めて説明できる
3.4. 4⃣鑑定評価の意義
3.4.1. (1)「適正価格」を「鑑定士」が把握する作業に代表されるように
3.4.1.1. 専門家によって可能な仕事
3.4.1.1.1. 専門的だよ
3.4.2. (2)「専門家の判断」であり、「意見」
3.4.3. (3)「秩序の中」で「あり所」を指摘すること
3.4.3.1. 「意義」は大きい
4. 4節_不動産鑑定士の責務
4.1. 1⃣基本理念
4.1.1. (1)「土地」は「理念」に即して取引されるべき、「投機対象」×
4.1.1.1. 投機はダメですよ
4.1.2. (2)「鑑定士」は「基本認識」にたって「鑑定評価」する
4.1.2.1. 法律を押さえてね
4.2. 2⃣社会への責任
4.2.1. (1)「鑑定士」は「地位」を「法律」によって認知・付与される
4.2.1.1. 法律で独占業務を与えているから
4.2.2. (2)「鑑定士」は
4.2.2.1. ①「社会的意義」を理解し、「責務」を自覚し
4.2.2.1.1. 重要なことを自覚し責任もて
4.2.2.2. ②「実践」をもって、「社会期待」に報いる
4.2.2.2.1. 期待に応えるために行動しなさい
4.3. 3⃣責務
4.3.1. 「鑑定士」は
4.3.1.1. (1)「規定・良心・誠実」に「鑑定評価」を行い
4.3.1.1.1. ルールを守り
4.3.1.2. (2)「専門家×行為」をしてはならない
4.3.1.2.1. 恥ずかしいことはしちゃダメ
4.3.1.3. (3)「理由」なく、「秘密」を他に漏らさない
4.3.1.3.1. 秘密大事
4.4. 4⃣遵守事項
4.4.1. さらに「次の事項を遵守」して「資質向上」に努める
4.4.2. (1)勉強
4.4.2.1. ①「知識・経験・判断力」が統一されて、「的確鑑定評価」が可能
4.4.2.1.1. 知識大事だから
4.4.2.2. ②「勉強・研鑽」で体得し、「進歩改善」に努力
4.4.2.2.1. 勉強しろよ
4.4.3. (2)信頼向上
4.4.3.1. ①「依頼者」に対して「誠実に説明」を行い
4.4.3.1.1. ちゃんと説明して
4.4.3.2. ②「社会」に対して「実践活動」をもって「理解を深める」により
4.4.3.2.1. 行動することで
4.4.3.3. ③「信頼」を高めるように努力
4.4.3.3.1. 信頼向上
4.4.4. (3)公平
4.4.4.1. 「鑑定評価」にあたっては、「理由」に関わらず「公平態度」を保持する
4.4.4.1.1. えこひいきはダメよ
4.4.5. (4)注意
4.4.5.1. 「鑑定評価」にあたっては、「注意」をはらう
4.4.5.1.1. 油断するな
4.4.6. (5)利害関係
4.4.6.1. ①「限度超・鑑定評価」を引き受け
4.4.6.1.1. 能力がたりない
4.4.6.2. ②「縁故・特別関係」を有する
4.4.6.2.1. 忖度しちゃう
4.4.6.3. 「公平を害する恐れ」があるとき
4.4.6.4. 原則として「鑑定評価」を引き受けてはならない
4.4.6.4.1. 例外はあるけどね
