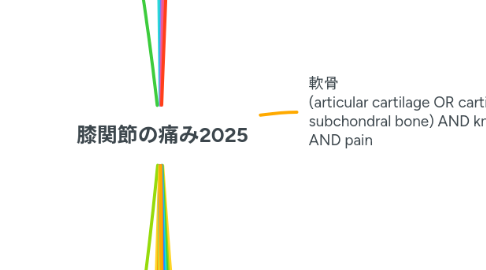
1. 半月板
1.1. 評価
1.1.1. ・腫脹の有無 圧痛がある場合は腫脹の有無も必ず確認 手術適応がある場合は腫脹を伴うため、膝蓋跳動で水腫、あるいはエコーで確認 ・関節水腫は関節原生筋抑制の原因となり、大腿四頭筋の興奮性を低下させるため、機能面にも直接影響する https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28992769/ https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11194097/ https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8822681/ https://www.nature.com/articles/ncprheum0709 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19954822/ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3600920/ https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/6712434/ https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7063526/ 関節原生筋抑制(AMI):膝関節の腫脹、炎症、疼痛などにより、大腿四頭筋の最大随意収縮能やH反射が低下することを指す 関節内圧の上昇による伸張刺激がメカニズムとして考えられている 関節内圧は最大伸展位と最大屈曲位で最も高くなるため、可動域の最終域に向かって抑制の影響は大きくなる
1.1.2. 可動域 半月板由来の痛みの場合、多くは屈伸の最終域で痛い 特に中節〜後節の損傷が多いことから、屈曲最終域で疼痛と制限を認める場合が多い、屈曲最終域で痛みがない場合は半月板以外の問題を疑う 過伸展時の痛みも重要、大腿骨のロールフォワードによって半月板の前方が前に牽引され、結果的に後方も引っ張られて痛みの原因になる 深屈曲位では半月板後節は大腿骨顆部に挟まれ、疼痛を訴える場合がある https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15598453/ 下腿の前方引き出しや内旋、外旋操作によって疼痛の減弱、増悪がないか確認することはROM制限の原因の推察と治療のヒントになる https://jglobal.jst.go.jp/detail?JGLOBAL_ID=201202218352110453
1.1.3. McMurrayテスト https://bjssjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/bjs.18002911612 半月板後節を大腿骨顆部に引っ掛けることを意図したテスト 膝深屈曲位で内反/外旋、外反/内旋を加え、その状態で伸展させていく 膝を把持する手はクリックを感じるために関節裂隙を触れておく 疼痛を生じる角度より浅い屈曲角度で行う 引っ掛かりを感じた場合は陽性
1.1.4. Apleyテスト https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20284687/ 腹臥位で膝を90度屈曲させ、足部から膝へ圧迫ストレスを加える 足部を通じて膝へ内旋/外旋を加え、疼痛が誘発されたら陽性
1.1.5. 4つの回旋弛緩性パターン
1.1.6. 立位アライメント評価 内反、外反、パテラ内側偏位、距骨外旋
1.1.7. 荷重位ストレステスト knee in、knee out、前方回旋テスト、クロス回りテスト
1.1.8. ・歩行分析 内側半月板:LRの内反、パテラ内側偏位、TStの距骨外旋 外側半月板:LRの外反、TStの距骨外旋 ・varsu thrustは内側半月板逸脱と関連する可能性がある https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31350063/
1.1.9. 筋力 股関節伸展や外転、外旋筋力の低下は動作中の膝外反モーメントや膝外反角度の増加と関連 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22894982/ https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26110347/ https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31902735/
1.1.10. 圧痛 裂隙を横から、中節〜後節が多いのでそこを中心に確認 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17939613/ https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25724195/ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3204363/ 半月板自体の圧刺激による反応というよりは損傷茎部の関節包の圧痛や関節内の炎症反応として考えられている https://mol.medicalonline.jp/library/journal/download?GoodsID=ap5orthe/2016/002903/002&name=0013-0021j&UserID=1100003326-06 そのため、半月板損傷に特異的な所見ではない
1.1.11. 膝後部内側半月板根部断裂のある患者において、超音波検査で患者の体位が内側半月板の突出を増加させる
1.1.11.1. MMPRTの患者は臥位で下肢を4の字にすると、MMEが他の肢位と比べて増加した
1.2. 機能解剖
1.2.1. ・円状半月板 発生率は3~5%、多くは外側に発症、通常の半月板より軽微な外力で損傷する ・外側円板状半月板(DLM)は最も頻繁に認められる半月板の解剖学的変異。関節鏡所見+臨床所見を加えた分類 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10067999/
1.2.2. 大腿骨のロールフォワード
1.2.3. 内側はMCLの深層と連続性を持ち、外側は前半月大腿靭帯(ハンフリー靭帯)と後半月大腿靭帯(リスベルク靭帯)が付着 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16228178/ https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21503653/
1.2.4. 外側半月板後角には膝窩筋腱が付着し、内側半月板後角には半膜様筋腱が付着 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22098726/ https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/14977657/ 半月板の安定性や可動性に関与
1.2.5. 膝窩筋腱複合体の解剖学、機能、およびリハビリテーション
1.2.6. 膝関節全置換術後の痛みの原因としての膝窩腱の衝突:系統的レビュー
1.2.7. 膝窩筋腱の形態に関する現在の概念とその臨床的意義
1.2.8. 膝窩筋の in vivo 超音波イメージング: 機能特性の調査
1.2.8.1. ・一般的には、安静時に大腿骨の下で脛骨を内側に回転させ、脛骨の上で大腿骨を外側に回転させる ・下腿内旋で筋厚増加 ・屈曲時に筋厚増加が70%、伸展時に増加が30%、変化なしが20% ・膝窩筋の経路に関する以前の研究では、膝窩筋の大腿骨付着部を調査し、膝関節側副靱帯付着部下方型(49.4%)、前方下方型(24.7%)、後方型(25.9%)の3種類の付着部があると報告 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21837463/
1.2.9. 潜在的な臨床的および生体力学的重要性を伴う膝窩筋腱の新しい形態学的分類の提案
1.2.10. 膝窩隆起は、関節内の膝窩腱が後外側膝の安定性をサポートしていることを示しています
1.2.10.1. 軽度屈曲位で膝関節の安定性に対してより積極的に作用
1.2.11. 機能解剖からみた理学療法の展開
1.2.11.1. ・膝屈曲角度を増していっても膝窩筋と大腿骨が接触することはなかった →屈曲角度の増加による挟み込みは痛みの原因ではない可能性が高い ・膝屈曲角度の増加で腓腹筋内側頭はボリュームの大きさから起始部の折り曲がりによる筋自身による圧迫が認められる →柔軟な筋肉なら折れ曲がりでも圧を分散できるが、柔軟性が低下していると圧を分散できず、局所的な圧が加わることによる疼痛が起こっている可能性がある ・骨盤後傾によるイニシャルコンタクト、加齢などによる股関節伸展機能の低下により、股関節伸展による推進力の低下が腓腹筋によるCKCにおける膝屈曲モーメントを強くする、腓腹筋本来の働きではないため、その結果腓腹筋筋硬結を生む ・膝窩筋は歩行中、踵接地の直前から働き、立脚期の3/4まで継続し、脛骨の内旋保持に働く https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/908724/ ・膝窩筋は側方動揺および回旋動揺が生じた際に制動要素として働く可能性が高く、過負荷による筋の過緊張を強いられる
1.2.12. 膝窩筋、ハムストリングス筋群の筋電図解析
1.2.12.1. ・立脚初期に膝を過伸展またはロックしないように活動 ・荷重時、膝屈曲角度が増すにつれ、脛骨前方移動量が増え、大腿四頭筋の活動が増加するため、膝窩筋は大腿四頭筋と拮抗する形で脛骨前方移動を制動しているのでは
1.2.13. 膝窩部痛に対する考え方と運動療法への展開
1.2.13.1. ・膝関節他動屈曲に伴う膝窩部痛は,膝関節屈曲運動時に本来出現すべき半月板の後方移動が,何らかの原因により障害された事に伴うmeniscus impingement, もしくは,膝関節屈曲により弛む後方関節包のimpingementがその病態として予想される →これら不安定刺激がきっかけで生じる,半膜様筋や膝窩筋の反射性攣縮が持続した結果生じる,筋内圧の上昇もその要因のひとつと推察される ・完全屈曲時の外側半月板は大腿骨外側穎からの挟み込みを避けるかのごとく後方に移動し,あたかも脱臼した状態となっており、これは脛骨外側穎の関節面がフラットで後方傾斜がある事, 膝関節屈曲に伴う大腿骨穎部のroll-backが内側に比べて大きいため穎部自体から後方へのpush out forceを受ける事,内側半月板はMCLと結合があるが、外側半月板はそのような結合がなく可動性に富む構造であることが理由 →膝窩部痛が生じている患者では,これら生理的な半月板の運動性が欠如した結果,impingementが生じやすい環境にある ・膝関節屈曲運動に半膜様筋が作用する事は,屈曲に伴う内側半月板の後方移動を能動的に引き出すとともに,緩んだ後方関節包靱帯を引き出す関節筋としての機能も重要 ・外側半月板の後方移動 →①LCLの後方、大腿二頭筋腱の前で外側半月板後角を触診、②もう一方の手で膝窩筋の走行に合わせる、③起始と停止が最短距離で近づく運動面を他動的に再現、④徐々に他動運動に児童運動を合わせてもらう ・内側半月板の後方誘導ならびに後方関節包靱帯の引き出し操作 →①MCLの後方、薄筋の前方で内側半月板後角を触診、②もう一方の手を膝窩に当て、大腿骨長軸と平行になるように膝屈曲に対して抵抗をかける ・歩行時や走行時の膝窩部痛は、foot flat~mid stanceにかけての膝伸展による膝窩筋の遠心性収縮による筋内圧上昇、heel contact~foot flatにかけて本来は膝屈曲に伴う下腿内旋が起こるが、 下腿外旋例では屈曲に伴い外旋が生じ、膝窩筋のoveruseが起こっている ・外傷ならびに膝関節手術後生じる膝後外側角部痛の特徴と病態解釈 →①歩行時の疹痛は、foot flatからMid stanceへ移行する膝関節伸展時に一致する事,②膝窩筋には通常圧痛はなく,ファベラ腓骨靱帯に限局して強い圧痛所見がある事,③疼痛が膝関節後外側角に限局しており, 患者はその疹痛部位をone point indicationできる事,④dynamic alignmentは立脚時の過度な大腿内旋を伴うknee-inを認める事,⑤屈曲拘縮の改善とともに疹痛は軽減していく事が挙げられる ・ファベラ腓骨靱帯は膝関節の屈曲により弛緩し,伸展により緊張、内旋により弛緩し,外旋により緊張する ・膝関節の完全伸展には,screw home movementに伴う下腿の外旋誘導が大切。軽度屈曲拘縮がいつまでも改善しない場合には,終末外旋運動の制限因子である,ファベラ腓骨靱帯を中心とした 後外側支持機構への選択的なストレッチング(下腿外旋、膝伸展)が有効
1.2.14. 半月板の辺縁は血管領域で繊維軟骨に、中心は無血管領域で関節軟骨に類似した特徴を持つ https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21764438/
1.2.15. ・Ⅰ型コラーゲンが大部分を占め、半月板内のコラーゲンの90%以上に相当 https://febs.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1016/0014-5793(83)80592-4 ・コラーゲンは中心1/3よりも辺縁2/3に多い https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.3109/03008208709005619 ・辺縁領域ではⅠ型コラーゲンが大部分を占め、中心領域では60%がⅡ型コラーゲン、40%がⅠ型コラーゲンから構成 →これは半月板の中心領域には圧迫や剪断ストレスが加わりやすく、辺縁領域には主に引張ストレスが加わることを反映しているものと考えられる
1.2.16. ・辺縁部2/3と前角・後角に自由神経終末(侵害受容器)や固有受容器が存在 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10100118/ https://bmcmusculoskeletdisord.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12891-019-2706-x ・辺縁1/3では中間1/3と比較して密に受容器が存在するが、中心1/3は神経支配を欠く https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10100118/ ・中間1/3には血管は分布しないが、受容器が存在する https://bmcmusculoskeletdisord.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12891-019-2706-x ・前角、後角では全体的に神経支配が豊富 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10100118/ https://bmcmusculoskeletdisord.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12891-019-2706-x
1.2.17. ・片脚立位では主に内側半月板に負荷が加わる https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0268003305000203 ・歩行の荷重応答期では主に外側半月板に負荷が加わり、立脚終期を迎える頃に内、外側半月板に同等の負荷が加わる https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23572353/ https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24296275/
1.2.18. ・半月板はISAKOSの定義によると、7つのカテゴリーに分類される (損傷の深さ、辺縁位置、前後位置、膝窩筋裂孔・中央の損傷、損傷パターン、半月組織の質、損傷の長さ) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26724644/
1.2.19. 膝関節のsecondary stabilizerとしての半月板の役割 ・正常な膝では内外半月板を全切除しても脛骨の前方弛緩性はほぼ増加しない https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/6896333/ https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2925713/ ・しかし、ACL不全例では内側半月板を切除することにより、Lachmanテストによる前方弛緩性が優位に増大する https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20530720/ ・一方、外側半月板を全切除しても前方引き出し負荷を加えた際の前方弛緩性への影響は小さいが、pivot shiftテストの際の前外側弛緩性が増大する ・ACL不全膝において、半月板の膝関節安定性への貢献は大きく、半月板へのストレスは増大することになる
1.2.20. 正常では屈曲に伴い脛骨の内旋が生じ、半月板は大腿骨-脛骨間を埋めて適合性を高めるように脛骨上を後方へ移動する 外側半月板、特に前節の動きが大きい https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10067999/ https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18183628/ 深部屈曲位では外側半月板は変形しながら脛骨高原後方へ亜脱臼し、内側半月板は大腿骨内顆に挟まれながら変形する https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15598453/ 内側半月板は脛骨内旋時に前方へ、外旋時に後方へ動き、外側半月板は内旋時に後方へ、外旋時に前方へ動く https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8188723/
1.2.21. Qアングルは屈曲に伴う脛骨内旋で90度屈曲位ではおおよそ0度となる 脛骨粗面に手を当てながら他動的に膝を屈伸させると屈伸に伴う回旋を評価できる
1.2.22. 前角と比較して後角の損傷リスクが高いことは、前角と比較して可動性が低下し、屈曲時の負荷が増加することと関係している可能性がある https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10067999/
1.2.23. 半月板根部断裂の修復 - 内側半月板根部修復と外側半月板根部修復には違いがありますか? 系統的レビューとメタ分析
1.2.23.1. ・内側半月板はその全長に沿って周縁で関節包に付着していますが、外側半月板の付着は膝窩筋腱の領域で途切れている ・内側半月板は深内側側副靱帯本体に付着していますが、外側半月板と外側側副靱帯の間には同様の関係は存在しない ・半月板大腿靱帯(ハンフリー靱帯およびリスバーグ靱帯)は、外側半月板の後角の追加の骨付着部として機能しますが、同様の構造は内側には存在しない ・内側半月板根断裂は中年および高齢の方が多く、変性が原因、外側半月板は活動的な若年者に多く、外傷が原因の場合が多い ・多くはACL損傷も合併 ・内側半月板根断裂修復後の残留半月板の突出量は、外側半月板根断裂修復後に観察された突出量よりも有意に大きいことがわかりました(3.8± 1.7 mm vs 0.9 ±1.2mm、p < 0.001) ・再評価 MRI で評価された半月板修復の治癒状態も、外側根修復群と比較して内側歯根修復群の転帰が著しく悪い(完全治癒57% 対 完全治癒 86%、p < 0.001) ・術後リショルムスコアと IKDC主観スコアの有意差も、内側半月板根修復コホートと外側半月板根修復コホートの間で観察され、外側修復コホートの方がより優れた機能的転帰をもたらしました (リショルムスコア:82 ± 15 vs 93 ±10、p < 0.001; IKDCスコア: 72 ±16 vs 90 ± 12、p < 0.001) ・内側半月板後歯根断裂のある患者は高齢であり(55± 9 歳 vs 28 ±9 歳、p < 0.001)、主に女性であり(82%vs 34%、p < 0.001)、孤立した歯根断裂として発生する可能性がより高かった(99.7% 対9%、p < 0.001)。 一方、外側半月板後歯根断裂を有する患者は著しく若く、主に男性であり、ACL再建手術を伴う外傷を伴う可能性がより高かった ・内側、外側ともに修復術後に突出量が減少、外側 (1.4 ± 1.1 mm、18 膝) と比較して内側 (4.8 ± 1.9 mm、18 膝) で多かった ・適切な後歯根の存在下では、内側半月板と外側半月板の間で半月板の突出量に差がなかったと報告した(0.338mm対0.235mm;p=0.181) しかし、両方の歯根で後歯根剥離を誘発すると、内側半月板は外側半月板と比較して半月板の突出量が一貫して増加しました(2.233mm vs 0.471 mm; p < 0.0001) ・再評価 MRI で評価された完全治癒した膝の割合は、外側と比較して内側根修復後の方が有意に低いことがわかりました (57% vs 86%; p < 0.001) ・後外側半月板根部のみの切断後の死体膝の生体力学的研究において、47 人は、膝の外側コンポーネントの接触圧力に顕著な増加は見られませんでした。しかし、半月板大腿靱帯が切断された場合、接触圧力の大幅な増加が認められ
1.2.24. 人間の膝における脛大腿骨の接触力学に対する半月板の影響: 系統的レビュー
1.2.25. 内側半月板後歯根断裂:どこまで進んで、何が残っているのか?
1.3. リスクファクター
1.3.1. 退行性変性に伴う損傷は高齢、男性、高値のBMI、膝に過度な負担がかかる日常生活・仕事動作を行うものに好発する https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18784100/ https://www.jrheum.org/content/36/7/1512 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12533565/ https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11916889/ https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11908573/ https://bmcmusculoskeletdisord.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12891-017-1886-5 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/14504371/
1.3.2. 膝OAに伴う軟骨厚の減少は半月板と軟骨の接触領域を減少させ、半月板逸脱の危険性が高まる https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27936066/
1.3.3. 階段昇降や膝立ち、しゃがみ込み動作は退行変性損傷のリスクを増大させる https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23628788/
1.3.4. 軸圧がかかった状態での膝屈伸や深屈曲が半月板へのストレスを高める 脛骨外旋と膝屈曲の組み合わせで、内側半月板後角への負荷が増大する https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22085731/ →下腿外旋位で日常生活動作を行うことは、退行変性損傷リスクを高める
1.3.5. ・hoop機能の破綻による半月板逸脱がOA進行に関連すると考えられるようになっている https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23733830/ ・3mm以上の逸脱は大きな横断裂や複雑断裂、後角損傷によるhoop機能の破綻を示唆、臨床上も優位な逸脱と捉えられている https://ajronline.org/doi/10.2214/ajr.183.1.1830017 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18815238/ https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15316679/
1.3.6. 変形性膝関節症における半月板の病状、軟骨喪失、関節置換術と痛みの関係:系統的レビュー
1.3.6.1. ・半月板の突出は、年齢、性別、BMI とは無関係に、膝 OA の構造的進行および構造的重症度と関連 ・半月板の突出の存在がTKA発生リスクの増加と関連 ・半月板断裂(内側または外側の半月板の前部、中央部、または後部)の存在および増加は、構造的進行(MRI軟骨欠損)と関連 ・前角ではなく、後角で発生した場合、膝 OA の構造的進行および構造的重症度と関連 ・半月板の突出は、年齢、性別、BMIとは無関係に、WOMAC膝痛の変化と関連しているようだが、臨床的に意味のある痛みの変化ではないし、質の高い証拠も不足している ・半月板の突出は膝OAの痛みの重症度と断面的に関連
1.3.7. 半月板根断裂の時系列の調査:内側半月板後根断裂は突出を引き起こすのか、それともその逆なのか?
1.3.7.1. ・MT靱帯断裂とそれに伴う半月板の突出がMMPRTよりも前から発生しており、突出とMT靱帯の異常が内側半月板後角根付着部の応力を増大させ、MMPRTを引き起こす可能性があるという仮説を裏付けた ・内側半月板の押し出しは複雑ですが、一度押し出されると急速に進行する傾向があるということは文献で比較的コンセンサスがある ・分析した膝の 96.3% で突出が進行し、平均追跡期間 1.7 ± 1.6 年間で平均突出が 3.3 ± 1.1 から 5.5 ± 1.8 mm に大幅に増加した
1.4. 疼痛
1.4.1. 炎症
1.4.1.1. IL-1、TNF-αが半月板、滑液で過剰発現、過活動
1.4.1.2. 神経成長因子、サブスタンスPが滑液で増加、ヒト研究による知見では半月板で増加するかは不明
1.5. 治療
1.5.1. ・可動域制限を改善する ・半月板の力学的負荷を改善する ・如何に半月板へのストレスを軽減するか
1.5.1.1. 伸展制限 IFP、半膜様筋、後外側支持機構が制限因子として多い
1.5.1.2. 屈曲制限 屈曲強制によって膝窩部周辺に痛みや張り感を感じる場合、半月板と周囲組織の滑走障害を疑う 下腿内旋を入れつつ屈伸を繰り返すことで、半月板と周囲組織との滑走を促すことができる
1.5.1.3. モーターコントロール 荷重時の内外や回旋による偏りがなく真っ直ぐ荷重できるように 斜めに荷重が加わると彎曲や回旋力が加わってしまう スクワット、ランジ、フロント/バックターン ターンは膝とつま先の位置が一体となるように行う
1.5.2. 内側半月板後根断裂の修復後のリハビリテーション:文献の系統的レビュー
1.5.3. 内側半月板後歯根断裂の修復と非修復: 臨床結果および X 線検査結果を含む、患者の選択基準の系統的レビュー
1.5.3.1. ・修復治療、未修復治療どちらも良好な機能的転帰を示した ・重度の軟骨変性、内反アライメントは治療法に関係なく予後不良 ・半月板切除後は痛みの改善率が低い、満足度が低い、失敗率が高い、関節形成術への転換、重篤なIKDCスコアなど予後不良 ・MMPRT修復後にKLグレードが進行した患者が多かった
1.5.4. 変形性膝関節症を伴う内側半月板後角縫合の成績
1.6. 変形性膝関節症における半月板変性症:病理学から治療まで
1.6.1. ・半月板を完全に除去すると、無傷の膝と比較してコンパートメントの接触面積が40 ~ 50% 減少し、ピーク接触応力が 2 ~ 3 倍増加することが確認されており、これが応力の増加に寄与する可能性があります。 関節軟骨と軟骨下骨の両方に集中 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/6894212/ ・フープ機能の観点から、内側の自由端から外周までメニスカスを横切る半径方向の裂け目は、荷重分布の大幅な損失をもたらします https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22074620/ ・外側半月板(LM)後根断裂は急性ACL損傷を伴うことが多い https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25502611/ https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28484790/ ・変性半月板病変(DML)は、35歳以上の患者において膝外傷の病歴がなく発生する半月板病変として定義 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5672871/ ・MRIでMMの損傷がある患者は損傷のない人と比べてX線でのOAが著しく進行している →DMLがOAの開始と高度に相関していることを示す https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26555215/ ・OAを発症した患者ではMM病変の割合は対照群と比較して有意に高くはなかったが、MM突出が一般的であった https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23733830/ ・半月板の突出により脛骨の被覆が減少し、それによって軟骨の耐荷重が増加する。関節腔の狭小化と強く相関 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10484216/ https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16868968/ ・OAを発症した患者のMM断裂または変性の割合は対照群と比べて有意に高くはないが、MMEは対照群よりOA方が一般的であった →MMEの方がOA進行、痛みのリスクファクター? https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23733830/ ・膝の痛みはMMEのないOA患者よりもMMEのあるOA患者で頻繁に見られた https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21842432/ https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25497320/ ・MMPRTはMMEの強力な原因、フープ機能の喪失とOAの進行を促進する、MMPRTはOAの強力な危険因子 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18762653/ ・超音波は半月板の突出を検出するのに役立つ https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21905003/ https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12905471/ ・半月板切除は切除量が限られていたとしても、対照群と比較してOAのリスクを高くする https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12905471/
2. 鵞足
2.1. 評価
2.1.1. 圧痛 縫工筋、薄筋、半腱様筋
2.1.2. 筋の伸張テスト →膝の屈伸を加えると疼痛を誘発しやすい 縫工筋:股関節伸展、内転、内旋 薄筋:股関節中間位、外転、膝伸展 半腱様筋:股関節屈曲、膝伸展
2.1.3. 非荷重位での下腿外旋偏位の有無 パテラと脛骨粗面の位置関係
2.1.4. 脛骨の前方偏位の有無 鵞足の伸張負荷を助長する
2.1.5. 立位アライメント 外反、過外旋、距骨外旋、後足部外反
2.1.6. 荷重位ストレステスト knee in、knee out、回旋テスト、クロス回りテスト
2.2. 治療
2.2.1. ・薄筋の過緊張と伸張性の改善 ・膝関節外旋の力学的負荷の改善
2.2.1.1. 薄筋の緊張緩和 ・最大伸張-最大弛緩の反復 ・薄筋-半膜様筋間に指を入れ、薄筋を側方に滑走させる
2.2.1.2. 鵞足の滑走 鵞足を徒手的に把持し、筋・腱の走行に対し直交する方向へ滑走させる 半膜様筋の内側が半腱様筋、半膜様筋の表層に薄筋、その上方に縫工筋
2.2.1.3. 大腿外旋エクササイズ 大腿内旋が優位で膝の過外旋を呈する場合は股関節の外旋可動域拡大、立位での外旋エクササイズを行う
2.2.1.4. 距骨外旋の抑制エクササイズ ・長母趾屈筋のストレッチ ・足部内転(踵を外側へ)
3. 伏在神経 saphenous nerve
3.1. 機能解剖
3.1.1. 伏在神経は内側広筋と大内転筋の筋膜内(内転筋菅)を走行し膝蓋下枝と内側下腿皮枝に分岐する 伏在神経の表層は縫工筋が覆っている
3.1.2. 膝蓋下枝は縫工筋後縁を回り筋表面を前方に向かうもの(41.7%) 縫工筋筋腹を貫通して筋表面の前方を走るもの(52.8%)
3.1.3. 内転筋管通過後には内転筋結節直上へ向かう関節枝と膝蓋骨遠位へ向かう膝蓋下枝、下腿部への下腿内側皮枝に分岐し、大腿遠位内側から膝関節、下腿内側の感覚を支配している
3.2. 評価
3.2.1. 圧痛 内側広筋と大内転筋の間、膝蓋骨より拳1個分ほど近位
3.2.2. 牽引刺激 知覚領域に牽引刺激を加えて痛みを誘発する 伏在神経障害を有する場合、脂汗が出るほど強い痛みを訴える
3.2.3. 縫工筋の伸張テスト 股関節伸展、内転、内旋、膝関節伸展
3.2.4. 立位アライメント 後足部角、レッグヒール角、膝蓋骨の向き、距骨の外旋、足部アーチの低下
3.2.5. 荷重位ストレステスト knee in、前方回旋、クロス回り
3.2.6. 歩行分析:股関節屈曲モーメント増大が問題→縫工筋が過緊張するから 遊脚期の股関節屈曲位の荷重(骨盤前傾増加)、骨盤後方回旋、前足部内反、ヒップハイカー(骨盤挙上)
3.3. 治療
3.3.1. ・縫工筋の過緊張と伸張性の改善 ・皮膚と筋膜の滑走障害の改善 ・遊脚前期の股関節屈曲モーメント増大の改善
3.3.1.1. 縫工筋の筋緊張緩和 最大伸張-最大弛緩、ストレッチ 股関節屈曲、外旋、膝屈曲位で短縮
3.3.1.2. 縫工筋の徒手滑走 縫工筋繊維と直行する方向へ滑走させる
3.3.1.3. 皮膚、筋膜の徒手滑走
3.3.1.4. 股関節伸筋のストレッチ
3.4. 変形性関節症における疼痛管理へのメカニズムに基づいたアプローチに向けて
3.4.1. 膝OAの痛みは侵害受容性疼痛から神経障害性疼痛へと変化する
3.5. 地域膝OAコホートにおける神経障害性疼痛症状
3.5.1. 膝OAを発症している高齢者の約1/4に神経障害性疼痛が見られた
3.6. 内側変形性膝関節症における膝痛の位置:パターンと自己申告の臨床症状との関連
3.6.1. 膝の後内側に痛みを訴える人の22%に神経障害性疼痛がみられた
3.7. ラットのMIA誘発性変形性関節症における膝関節関連機械受容一次求心性ニューロンのC線維の自発発火とA線維の機械的感受性の増加
3.7.1. ・Aδ繊維(AM)が機械的刺激に反応するのに対し、C繊維(CM)は伏在神経の自発放電に関与していた ・OAは機械的刺激だけではなく、 神経障害性疼痛の自発痛も問題となるかも ・予測できない痛みに神経障害性疼痛が関与するのではないかという基礎研究
4. 半膜様筋
4.1. 扁平足を呈し膝関節伸展制限を伴う高齢者に多い
4.2. 機能解剖
4.2.1. 脛骨内側顆、斜膝窩靭帯、膝窩筋膜、膝後方関節包、後斜靭帯、内側半月板、外側半月板など多くの部位に付着
4.2.2. パワーを発揮するよりは、屈曲時の半月板や関節包挟み込み防止など機能的な役割が大きい
4.2.3. 停止部の腱周辺では滑液包が存在するため、炎症や癒着が起こりやすく、疼痛や可動域制限の原因になる
4.2.4. 腱停止部はanterior armと呼ばれる 膝関節内側裂隙の1-1.5cm遠位に半膜様筋溝と呼ばれるanterior armが侵入する溝があり、圧痛好発部位である
4.2.5. 半膜様筋と腓腹筋内側頭は部分的に繊維性結合している 半膜様筋および腓腹筋に短縮や過緊張があると滑走性低下、摩擦刺激で可動域制限や痛みの原因となる
4.2.6. ハムストリングスの力と長さの関係と、角度特有の関節トルクに対するその影響: 物語的なレビュー
4.2.7. 遠位半膜様筋腱の関節鏡視下解剖:後内側の不安定性とランプ病変に関する解剖学的視点
4.3. 評価
4.3.1. 圧痛評価 anterior arm 鵞足との鑑別がポイント
4.3.2. 筋伸張テスト 半膜様筋の伸張:股関節屈曲位から膝伸展、足背屈
4.3.3. 扁平足の有無 扁平足だと立脚後期の蹴り出しが遅れ、足関節背屈で代償するため、腓腹筋にストレスが加わる
4.3.4. 立位アライメント 足部アーチの低下、距骨外旋
4.3.5. 荷重位ストレステスト knee in、knee out、回旋テスト、クロス回りテスト
4.3.6. 歩行分析 立脚後期の踵離地の遅延と距骨外旋に伴う下腿外旋(アブダクトリーツイスト)を評価
4.4. 治療
4.4.1. ・半膜様筋と腓腹筋の過緊張、滑走性の改善 ・膝関節外旋の力学的負荷の改善 ・立脚後期の踵離地の改善
4.4.1.1. 半膜様筋-腓腹筋の徒手滑走
4.4.1.2. 腓腹筋のストレッチ
4.4.1.3. リバーススクリューエクササイズ
4.4.1.4. 距骨外旋抑制 長母趾屈筋のストレッチ 足部内転エクササイズ
5. 滑液包
5.1. 機能解剖
5.1.1. 滑液包炎(bursitis)は外傷や感染、他の炎症症状から生じる滑液包の炎症と定義 病的変化は外傷性、炎症性、感染性、増殖性に分類される https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28190095/
5.1.2. 異常な滑液貯留、滑膜肥厚、あるいは双方による腫脹が原因となる過程によって病態が引き起こされる
5.1.3. 滑液包炎の最も一般的な原因は長時間の圧力 滑液包は硬い面と骨隆起の間でストレスを受ける 他には、滑液包に直接圧力が加えれた時の外傷
5.1.4. メカニズムとしては、外傷性、反復ストレス性、感染性がある 理学療法の適応は反復性のストレスによる滑液包炎
5.2. 評価
5.2.1. 膝蓋腱の患者主観的評価ツール、VISA-P https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9732118/
5.2.2. 疼痛評価 ・滑液包由来の疼痛は滑液包が存在する部位に限局するだけでなく、周囲に放散する場合もある ・隣接組織による繰り返しの圧迫ストレスが原因のため、圧痛検査は重要 ・滑液包を圧迫する方向への他動運動、関連する周囲筋に対して抵抗運動を行うことで疼痛が再現
5.3. 治療
5.3.1. ・滑液包にかかる圧を軽減する ・根本的な機能障害を改善する →滑液包自体は理学療法介入によって負荷耐用能が向上することはない ・機能的動作に必要な要素を細分化し、運動の基盤を整える ・改善した筋力、可動性を動作に反映させる
5.3.2. ・初期は荷重位では負荷が強すぎる場合があるため、目的の筋を単独収縮させるような運動から開始 ・積極的なストレッチは滑液包に圧迫ストレスを与え症状を増悪させる可能性があるため、まずは徒手的に滑走性を改善しておくことが重要 ・動作に直結するような荷重位でのトレーニングやROMの最終域まで挙上するようなトレーニングへ進めていく
5.4. 膝蓋上嚢
5.4.1. 水腫や関節血症、滑膜肥厚などの膝関節内の病態は膝蓋上嚢が膝蓋骨の上方や内外方に膨脹することが原因
5.5. 膝蓋前滑液包
5.5.1. 日常生活によるオーバーユースや慢性外傷から頻繁に生じる https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17981178/ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4529416/
5.6. 膝蓋下滑液包
5.6.1. 直接的な外傷もしくは慢性的なオーバーユース障害(聖職者の膝:clergyman's knee)から生じる可能性がある https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8010203/ https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17981178/
5.7. 腓腹筋-半膜様筋滑液包(ベイカー嚢胞)
5.7.1. 半月板損傷や十字靭帯損傷、関節水腫、変性疾患といった膝関節の病態と強く関連している https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15007568/ https://radiopaedia.org/articles/ultrasound-of-the-knee https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23622093/
5.7.2. 典型的に症候性と無症候性ともに膝関節内側後方に腫瘤が生じる 巨大な嚢胞は膝関節最大屈伸運動の制限となる可能性がある https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23622093/
5.8. 鵞足滑液包
5.8.1. オーバーユース障害が原因でランナーに生じやすい https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8010203/
5.8.2. 症状は内側半月板損傷もしくはMCL損傷に類似した膝内側の疼痛・腫脹が生じる https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8010203/
5.8.3. 鵞足滑液包炎の症状は滑液包炎自体よりむしろOAによって生じている可能性がある https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10898072/
5.9. 半膜様筋-内側側副靭帯滑液包
5.9.1. 滑液包の膨張と滑液包炎は急性もしくは反復性外相によって生じる 症状は膝内障もしくは他の膝内側滑液包の膨張に類似した膝内側痛と圧痛が生じる
5.10. 滑膜炎
5.10.1. 関節鏡検査を受けた初期OAの滑膜を調査し「OAに伴う滑膜」を 『①過形成(増殖)②線維化③Detritus-rich④炎症』の4つに分類しています。
5.10.2. 『滑膜変化のパターンは多様であり疾患の段階によって異なる』と報告しています。
5.10.3. 『滑膜炎はOAにおいて重要な病的役割を果たす。滑膜の炎症は関節不全の結果ではなく前段階であると考える』と報告されています。
5.10.4. 半月板、軟骨下骨、膝蓋下脂肪体が滑膜炎の進行に関与している可能性があります
5.10.5. 『OAの発症における滑膜の役割は軟骨破壊 →滑膜細胞が貧食 →滑膜が炎症→ 炎症性メディターを生産する』と考えられております。
5.10.6. 『OA関節内の炎症は、損傷した軟骨と炎症を起こした滑膜の間の相互作用の結果の一部である』と報告されています。
5.10.7. 『膝OAのIPFPおよび滑膜の両方にに炎症性浸潤・血管新生・肥厚など構造的変化を認める』と報告されています。
5.10.8. 進行性のOAは滑膜炎が特徴的であり、この特徴はレントゲン所見(JSW・JSN・K-L分類)と相関すると報告しています。
5.10.9. 「ラットの膝関節内にモノヨード酢酸(MIA)を注入し高用量MIA 群では滑膜組織の構造変化(線維症)を伴う持続性炎症が観察された」と報告されています
5.10.10. 『滑膜の炎症性浸潤の存在は患者アンケートによる膝症状の悪化と関連している』と報告しています。
5.10.11. 滑膜炎の存在は予後の悪化・疼痛感作に関連していると報告されています。
5.10.12. 『滑膜炎を有するOA患者の下行膝動脈(DGA)において異常な新生血管の発生を認めた。』と報告しています。
5.10.13. 『塞栓剤を投与して血管を消失させると滑膜炎の進行が抑制した。』と報告しています。
5.10.14. 『OA群は対照群よりも下行膝動脈(DGA)の血流速度(PSV)が有意に高く、そのcutoff値は33.9cm/sであった。』 『特異度=95.5% 感度=99.9%』と報告しています。 →滑膜炎の評価に加え、IFPの炎症を評価するのにも役立つ
5.10.15. 『滑膜炎の重症度はOAの疼痛に関与し、重症度と関節内水腫は関連している。』と報告しています。
6. 疫学
6.1. 変形性膝関節症の診断、病態生理学、治療に関する最近の最新情報
6.1.1. ・軟骨内には血管がないため、低酸素状態でも軟骨細胞は機能を維持できる ・OAは血管が発達、骨-軟骨間の生化学的伝達(サイトカイン、ケモカイン、アラーミンなど)を促進し、軟骨の劣化を促通する ・関節軟骨は水と有機細胞外マトリックス成分で構成、細胞外マトリックス成分上の受容体を介して、細胞周囲マトリックスの機械的ストレスと変化を検出
6.2. 日本の人口ベースのコホートにおける高齢者のX線撮影による変形性膝関節症の有病率と膝痛との関連性:ROAD研究
6.2.1. ・本邦の膝OA(K-L grade ≧ Ⅱ)の推定患者数は約2500万人 そのうち、膝痛を訴える患者は約800万人と推定されている ・重症度(K-L grade)が高くなるにつれ、膝痛を訴える割合が高くなる →膝痛そのものが変形進行のリスクファクター
6.3. 変形性関節症の疫学
6.3.1. OAの進行に最も影響する危険因子でエビデンスレベルの高い要因は 「肥満」と「関節損傷」
6.4. MRIでの構造変化と変形性膝関節症に関連する症状、機能、筋力との間には弱い関連性がある
6.4.1. ・痛みはX線よりもMRI所見で説明できることがあるが関連性は低い ・表を見るとBMLと滑膜炎が痛みと中等度関連している 軟骨の変性や菲薄化により関節の衝撃応力を吸収する能力が低下し、その結果、海綿骨や骨髄にかかる負荷が増えた結果による炎症や外傷性の変化を反映している ただ、一方でMRIはレントゲンよりも情報は得られるが、MRIで所見があっても痛みがない方もいるので、画像だけで判断はできないこともあるので、病態があっても痛みと必ずしも関連するわけではないことを頭に入れておくべき
6.5. 変形性股関節症と膝関節症における痛みの経験を理解する -OARSI/OMERACT の取り組み
6.5.1. ・膝OAの痛みは予測できる痛みから予測できない痛みへと変化する ・OAが進行すると、予測できない痛みが出てくる、予測できる痛みはこうしたら痛くなるんじゃないか?と自分である程度予測できるが、予測できない痛みは対処のしようがないのでADLにも障害が出てくる
6.6. ・痛み、こわばり、関節運動の低下、筋力低下など、4つの主な兆候が主に見られる https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33406330/ ・KOAの痛みは断続的であり、体重負荷に関連 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18296075/ https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31034380/ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2841860/ ・痛みを経験するKOA患者の滑液では、インターロイキン(IL)-6、腫瘍壊死因子(TNF)-α、MMP-13などの炎症性分子が常に上昇 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31009749/ ・治療後、炎症分子は大幅に減少したことから、滑液中の炎症分子は、KOA 関連の痛みの発生において重要な役割を果たす https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5622709/ ・関節変性中に組織が損傷すると、軟骨および軟骨下骨の深層に分布するこれらの神経線維が感覚を脳に伝達し、痛みを引き起こす https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22471357/ ・関節皮質の平坦化または陥没と考えられる骨の磨耗は痛みと関連 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6153568/
7. Spine-Knee Syndrome/Knee-Spine Syndrome
7.1. 地域在住高齢者の変形性膝関節症に対する脊椎不均衡の影響
7.1.1. 脊椎傾斜角度と膝屈曲角度は相関する primaryな要素(脊椎が原因?膝が原因?)は不明だが、最終的には同様のアライメントを示す
7.2. 骨盤傾斜と体幹傾斜: 脊椎変形のある成人の場合の 2 つの重要な X 線撮影パラメーター
7.2.1. 脊椎後彎は代償機構として骨盤後傾、股関節伸展、膝屈曲、足背屈を誘発する これらのメカニズムは膝関節の負荷を増大させ、膝OAの進行を助長する
7.3. 重度の変形性膝関節症患者における脊椎 - 骨盤 - 下肢軸の矢状方向の位置合わせ: X線撮影による研究
7.3.1. ・軽度膝OA 腰椎後彎で膝屈曲を代償させ、C7 plumb lineを前方化 ・末期膝OA 腰椎のみで補償が困難で、股関節と骨盤がアンバランスな状態
7.4. 成人における矢状バランスの臨床的問題
7.4.1. Sagittal vertical axis:SVAは加齢とともに増加(前方化)する (C7椎体中央からの垂線と仙骨後上縁の前後距離)
7.5. 変形性膝関節症患者における 脊椎骨盤アライメントと膝機能の関係
7.6. 病理学における脊椎骨盤組織と適応の生体力学的分析
7.7. 脊椎の矢状面バランスを保つのに寄与する代償機構
8. 膝OAに対する保存的理学療法戦略
8.1. 内側変形性膝関節症患者における膝関節の関節内構造に起因する痛みの臨床的特徴
8.1.1. ・内側型膝OAの歩行時痛を評価 ・関節ブロックが有効であった患者は61%、無効であった患者は31% ・無効だった31%は高齢で、罹患歴が長く、疼痛が広範だった ・疼痛の原因は関節内だけではないことを示す結果
9. 膝OA痛みの機序
10. 変形性関節症はなぜ痛いのか?
11. 侵害受容性疼痛
11.1. 骨棘
11.1.1. 変形性関節症における骨軟骨接合部および骨棘における神経血管浸潤
11.1.1.1. ・骨棘によって引き起こされる関節痛は骨棘部の骨髄腔に侵入した新生血管や神経線維に起因する
11.1.2. 膝の骨糸状症は健康関連の生活の質の低下を予測しますか? ROAD研究の3年間の追跡調査
11.1.2.1. ・骨棘と関節痛は関連する
11.1.3. 膝の骨棘における高信号は膝の痛みと関連しない
11.1.3.1. ・骨棘形成の程度は膝痛と関連しない
11.2. 関節狭小化
11.2.1. 症候性変形性膝関節症患者の定量的磁気共鳴画像法による疾患進行の長期評価: 臨床症状および X 線写真の変化との相関
11.2.1.1. ・関節狭小化と痛みに関連はなし
11.2.2. 変形性膝関節症における X 線撮影による関節腔の狭小化:半月板断裂と痛みの持続期間との関係
11.2.2.1. ・関節狭小化が強いほど半月板断裂の頻度が高く、膝の痛みが長く続く
11.2.3. 脛骨軟骨の量は変形性膝関節症患者の症状とどのように関係しますか?
11.3. 関節痛の基礎と臨床
11.4. MRI で定義された構造病理と全般的および局所的な膝の痛みとの関連性 - オウル膝関節炎研究
11.5. 変形性膝関節症の痛みの筋膜成分
12. 神経障害性疼痛
12.1. 神経障害性疼痛の特徴的な痛み
12.1.1. 1 知覚異常 2 痛みの質 3 痛みの強弱 4 痛みの時間的パターン
12.1.1.1. ・痛みと感じていなかった小さな刺激でも痛みと感じる ・痛み強度と痛みの持続時間が大きくなる
12.2. 膝OAでは神経障害性疼痛が生じていると報告されています。神経障害性疼痛の兆候がある膝OA患者は、動的内側負荷が高く、疼痛の重症度が高く、身体機能が悪かったと報告されています。
12.3. 『(DGAの)新生血管発生に伴って増殖する神経線維が痛みの発言に関与している。』と報告しています。
12.4. 膝OAの神経障害性疼痛の原因として考えられているものは、軟骨下骨の障害と持続する滑膜炎になります。 ・軟骨下骨を支配する神経の損傷が神経障害を引き起こす可能性があるという仮説が立てられています。 ・長期にわたる炎症性因子は、侵害受容ニューロンの持続的な活性化によって神経障害性疼痛の発症に寄与する可能性があります。
12.5. 機能解剖
12.5.1. 膝関節後部包の神経支配に関する解剖学的研究:画像誘導介入への示唆
12.5.2. 変形性膝関節症患者における下行膝蓋動脈血流速度の特徴
12.5.3. 膝の膝神経の超音波画像
12.5.3.1. ・膝神経は関節包に感覚神経を供給する
12.5.4. 慢性膝関節炎における膝神経ブロックの3針アプローチと5針アプローチの有効性と痛みおよび生活の質の比較:二重盲検ランダム化比較試験
13. MCL (MCL OR medial collateral ligament OR tibial collateral ligament) AND pain NOT ankle
13.1. 評価
13.1.1. 圧痛:伸張時と短縮時で評価 伸張→膝内旋・内反、短縮→膝外旋・外反 伸展位は後部繊維が伸張され屈曲位は上前部繊維が伸張 伸張時の方が疼痛が強い、短縮時に圧痛がある場合他の組織が原因の可能性あり
13.1.2. 外反ストレステスト 伸張ストレスをかけても痛みなく、圧痛はある場合は他の組織の問題か滑走障害が原因
13.1.3. 下腿の過外旋を評価 膝蓋骨位置と脛骨粗面の位置を評価
13.1.4. 立位アライメント ・膝蓋骨の内側偏位 ・距骨の外旋
13.1.5. 荷重ストレステスト ・knee in テスト ・前方回旋テスト(立位両脚支持で骨盤〜下肢を前方回旋させる) ・クロス回りテスト
13.1.6. 歩行分析 ・大腿内旋位荷重 ・アブダクトリーツイスト ・足部アーチの沈み ・下腿外方傾斜 ・足部外反
13.2. 治療
13.2.1. ・MCLと周辺組織との滑走障害や癒着 ・膝外反、もしくは過外旋を呈している
13.2.1.1. MCL周囲の癒着が疑われる場合 屈曲時の下腿内旋制限されるため、内旋入れながら最終屈曲位付近で屈伸動作を繰り返す
13.2.1.2. 伸展時に前方部で痛みや張り感がある場合はMCLとIFPの滑走性を促す
13.2.1.3. 伸展時にMCLの後方に痛みや張り感を感じる場合は半膜様筋の筋緊張緩和、滑走を促す →半膜様筋繊維を横方向へ牽引しつつ屈伸を繰り返す
13.2.1.4. 屈曲時にMCLに痛みや張り感がある場合は屈曲位で周辺組織を徒手的に後方へ滑走、下腿内旋を促す
13.2.1.5. リバーススクリューエクササイズ
13.2.1.6. 立位で股関節外旋エクササイズ →外旋位保ったまま片脚立位でも
13.2.1.7. 長母趾屈筋のストレッチ
13.2.1.8. 足部内転エクササイズ(座位&立位) 大腿内旋が強い症例には行わない
13.3. 機能解剖
13.3.1. MCLの表層と深層の間に半膜様筋腱が存在 摩擦負荷を軽減するための滑液包も存在
13.3.2. 表層には伏在神経、前方にはIFP
14. 評価
14.1. MOAKS
14.1.1. 膝 OA の半定量的全関節評価の進化: MOAKS (MRI 変形性膝関節症スコア)
14.1.2. WORMS→BLOKS→ MOAKS
14.2. KOOS
14.2.1. 膝損傷および変形性関節症アウトカムスコア (KOOS): 測定特性の体系的レビューとメタ分析
14.2.2. ・KOOS日本語版の妥当性と信頼性について確認されている https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21766211/
14.2.3. MCID:10 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32660618/
14.3. WOMAC 軟部組織損傷・障害の病態とリハビリテーション p509 ・MCID:5~6 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32660618/
14.4. OKS
14.4.1. ・OAの能力障害を測る尺度として世界各国で使用 https://www.semanticscholar.org/paper/Questionnaire-on-the-perceptions-of-patients-about-Dawson-Fitzpatrick/d5b2584be94a90dc00a89272955bd7ef10e131bd?p2df ・QOLと強い相関を持ち、臨床変化にも鋭敏な指標 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25441700/ ・痛みと活動制限に関する12の設問項目で構成5段階スコア ・合計点が高いほどに状態が良いことを表す ・OKSのMCID(臨床的に意味のある最小変化量)は4点 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25441700/
14.5. 近年はKOOSによる報告が増加傾向
14.5.1. 人工関節ではOKS、ACLRやHTOではKOOSをアウトカム
14.6. ・アメリカ理学療法士協会のガイドラインでは、IKDC-SKF、KOOSに加え、Lysholm scaleによる評価が推奨 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3204363/ ・心理状態や健康関連QOLの評価としては、SF-36やEQ-5D、KQOL-26が推奨 ・SF-36のMCID:5 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32660618/
14.7. 全ての疼痛に共通する評価 疼痛誘発動作の整理 症状との関連が疑われる動作パターンを修正、強調することで疼痛や不快感が減弱、増悪するかを確認し、仮説の裏付けを行う この時、複数の要素を同時に修正すると何が良かったか分からなくなるので、1つの要素ずつ行う
14.8. knee pain map
14.8.1. 内側変形性膝関節症における膝痛の位置:パターンと自己申告の臨床症状との関連
14.8.1.1. ・内側関節線 (n = 123、75%)、膝蓋骨腱(n = 62、38%)、および膝後部(n= 61、37%) が最も頻繁に報告された痛みゾーン ・最も頻度の高いパターンは、びまん性 (41%)、孤立した内側 (16%)、前内側 (12%)、および内側後部 (11%) の痛み ・WOMAC および ICOAP スコアは、前内側パターンと比較してびまん性パターンの方が高かった ・平均PainDETECTスコアは、前方内側の痛みと比較して、びまん性および内側後方の痛みの両方で高かった
14.9. 因果と相関
14.9.1. 目の前の現象を可能な限り明確にする ex.立ち上がりの時に膝内側が痛い ↓ 大腿骨が外旋、骨盤が後傾していた ↓ 大腿骨の外旋を止めると痛みが減少 ↕ 骨盤の後傾を止めると痛みが減少 (どちらを操作しても改善:相関)
14.9.1.1. 大腿骨の外旋、骨盤の後傾を生じさせる要因が他にあるはず (大腿骨の外旋や骨盤の後傾に一方向で影響する因子:因果)
14.10. 膝関節運動の評価(CKC)
14.10.1. ・大腿内旋と下腿外旋を誘導 ・大腿外旋と下腿内旋を誘導
14.10.1.1. 相対的な関節運動の操作 屈曲時にどのような操作を加えると対象者の愁訴の改善が得られるかを確認する 誘導の方向だけではなく、その強さやタイミングを考慮する
14.11. 運動恐怖(TSK-11)
14.11.1. ・重度膝OA患者の生活空間には身体機能に加えて運動恐怖が影響する ・末期膝OA患者では運動恐怖が強いほど生活範囲が狭い ・恐怖の対象は階段昇降、床からの立ちしゃがみ、歩行
14.11.2. 退院時の高レベルの運動恐怖症は、膝関節置換手術を受けた患者の短期的な機能的転帰に悪影響を与える可能性がある
14.12. FreKAQ
14.12.1. ・膝関節の主観的な身体知覚異常を評価する尺度 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28650969/ ・Neglect-like symptoms 「自肢の存在の認知」と「自肢の運動感覚の認知能力」が低下した状態 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7673771/ ・TKA術後3週の患者の36%、術後6週の患者の19%にNLSを認めた https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25101335/ ・慢性疼痛患者では、該当部位における体性感覚野の体部位再現が縮小する https://europepmc.org/article/PMC/3596443 ・体性感覚野の縮小の程度が疼痛強度と相関する https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15064892/
14.12.2. 「でも腫れているような気がする!」:客観的な腫れがないのに主観的な膝の腫れを訴える変形性膝関節症患者の頻度と臨床的特徴
14.12.3. 痛みを伴う膝の幻想的なサイズ変更は、症候性変形性膝関節症の鎮痛剤となる
14.13. 腫脹
14.13.1. ・客観的腫脹を認めた群は全例で主観的腫脹を認めた ・主観的腫脹を認めなかった群は全例で客観的腫脹を認めなかった ・客観的腫脹を認めないにも関わらず15例で主観的腫脹を認めた ・主観あり、客観なし群では安静時痛が強く、2点識別覚が増大、加えて主観あり、客観なし群では破局的思考や自己効力感が低下 ・客観的腫脹:エコーで測定した膝蓋上嚢の面積が90㎟以上、主観的腫脹:自分の膝が大きくなっている(腫れている)ように感じるを0=まったく、1=めったに、2=ときどき、3=しばしば、4=いつもの5段階で評価 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34765853/
14.14. 痛みの感覚的側面
14.14.1. 痛みの持続 炎症、強引な運動療法
14.14.1.1. 末梢からの強い侵害刺激の持続
14.14.1.1.1. 疼痛逃避行動(防御性収縮)による痛みの増強 痛み刺激により、αとγ運動ニューロンへの刺激が起こり、筋紡錘の感度が亢進し、わずかな伸張刺激でも筋収縮が生じる 筋収縮が持続することにより循環障害が悪化する、これにより、痛みが発生し悪循環がうまれる
14.14.1.1.2. 軸索反射 この刺激がポリモーダル受容器を興奮させ、痛みが損傷部位周囲に広がる CGRPは血管拡張作用があり、損傷部周辺に炎症が広がる
14.14.2. 不活動 不動、固定、非荷重など
14.14.2.1. 末梢からの刺激の減弱、消失
14.14.2.1.1. ギプス固定や非荷重、安静臥床などによって惹起される末梢組織の不活動状態はそれ自体が痛みを生み、慢性疼痛の発生要因になる
14.14.2.1.2. ・ギプス固定2週間で痛覚閾値が低下、その後も著明に低下している ・ギプス固定4週群 痛覚閾値の回復に4週間必要 ・ギプス固定8週間群 痛覚閾値の回復に14週間必要 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23818166/ ・ラットの不活動モデルでは表皮角質層の乱れや非薄化を認め、表皮厚の比較ではギプス固定1週間後は対照群と有意差を認めないものの、ギプス固定2,4週間後は対照群より有意に減少していた ・真皮上層に分布する末梢神経の分布密度を比較すると、ギプス固定2,4週間後は対照群より有意に増加した https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23098655/
14.15. エコー
14.15.1. EURO-MUSCULUS/USPRM膝関節用ダイナミック超音波プロトコル
15. 膝窩部痛
15.1. 膝関節屈曲制限の見方と運動療法 ~変形性膝関節症を中心に~
15.1.1. 完全に屈曲した膝: 解剖学的研究
15.2. オープンMRIを用いた膝関節の動作解析
15.3. 脛骨神経膝窩筋枝は神経が外側へ向けて走るため、その分布は脛骨後面の中央〜外側に多く存在する
15.4. 膝窩筋は屈曲110度以上の深屈曲で収縮して下腿内旋を引き起こす
16. 腸脛靭帯
16.1. 腸脛靱帯症候群患者における腸脛靱帯複合体のストレッチと解放:解説レビュー
17. 膝蓋下脂肪体
17.1. 変形性関節症を伴う肥満患者における従来の動的造影磁気共鳴画像法による膝蓋下脂肪体における膝痛と炎症の推定:横断研究
17.1.1. ・変形性膝関節症 (KOA) を伴う肥満患者の膝痛と膝蓋下脂肪体(IFP)の炎症の兆候との関連を調査 ・KOOSアンケートの疼痛サブスケールによって評価された疼痛と、IPFPにおける炎症を表すDCE-MRI上の灌流変数との間に統計的に有意な関連性が見出された ・KOOS疼痛とMOAKSホッファ滑膜炎との間には、統計的に有意な相関 ・MOAKS ホッファ滑膜炎とすべての灌流変数の間に統計的に有意な相関関係 ・IFPおよびMOAKSホッファ滑膜炎における炎症の重症度を反映するDCE-MRI上の灌流変数はKOA における疼痛の重症度と関連 ・IFPの重度の炎症がKOAの重度の痛みと関連 ・IFPは侵害受容神経線維によって豊富に神経支配されており、炎症によって引き起こされるこれらの侵害受容器の感作が、炎症を起こした関節における痛みや痛覚過敏の根底にある可能性がある ・灌流変数「炎症」は、痛みだけでなく、KOOS のすべての下位尺度とも良好な関連性を示し、より重篤な痛みと、より重度の膝関連症状および日常生活における機能障害、膝の両方の灌流の増加との間に関連性がある
17.2. 膝蓋下脂肪体の超音波画像による特徴。パイロットスタディ
17.3. 膝の膝蓋下脂肪体:局所脂肪は変形性膝関節症に良いのか悪いのか?
17.3.1. ・IFPの最大面積低下は関節腔狭小化、内側骨棘の存在、軟骨の体積低下、BML、膝の痛みと関連
17.4. 評価
17.4.1. IFP圧痛好発部位は膝蓋骨の内下方および外下方
17.4.2. 伸展・屈曲圧痛テスト 膝伸展位で圧痛再現、圧迫したまま屈曲すると疼痛は消失、軽減する →IFPが屈曲すると関節内へ入り込むから、膝蓋腱や膝蓋支帯が原因の場合は屈曲で伸張されるからむしろ圧痛が増強
17.4.3. 超音波エコー
17.4.4. IFPの繊維化があると膝蓋骨は低位となりやすい
17.4.5. 膝関節の捻れ:膝蓋骨に対する脛骨粗面の位置を評価 多くは膝関節が過度に外旋(大腿内旋+下腿外旋)しており、滑膜や関節包、靭帯、腱などの組織は伸張される →IFPが屈伸時に移動する経路が狭くなるため、摩擦負荷が大きくなる
17.4.6. 立位アライメント評価:膝蓋骨の位置、距骨の外旋を評価 通常は正面を向くが、大腿内旋していると膝蓋骨は内側を向く 足部を正面から見て、距骨の内外旋を評価(距骨が内側傾斜すると外旋)
17.4.7. 荷重位ストレステスト(降段動作、クロス回りテスト、両脚支持でのknee in・knee outテスト) 降段時は後脚の屈曲角度が大きくなり伸展モーメントが増大 クロス回りテストは膝関節が過度に外旋することで痛みを誘発しやすい knne in/knee outテストは立位で膝を軽度屈曲させ、各方向へ膝を誘導した際の疼痛を評価
17.4.8. 歩行分析 前半に膝外旋するタイプ(大腿内旋位荷重)、後半に外旋するタイプ(足部外反、アブダクトリーツイスト、足部アーチの沈み、下腿側方傾斜)
17.5. 治療
17.5.1. ・IFPの柔軟性を獲得 ・膝の捻れを改善し、IFPの移動経路を広げる ・IFPの移動経路の壁(関節包や腱)を柔らかくする
17.5.1.1. IFPの上下運動 膝蓋骨を徒手的に下制させ、セッティングを行い挙上させる 上がりきらない場合は徒手的に挙上を介助する
17.5.1.2. 膝蓋骨の引き上げ運動 屈曲位で膝蓋骨を引き上げ、伸展位に誘導し、引き上げたままセッティング
17.5.1.3. リバーススクリューエクササイズ 下腿内旋+大腿外旋誘導しながらセッティング
17.5.1.4. 大腿内旋抑制エクササイズ 立位で下腿に対して股関節外旋させる →大腿に何か挟むと良いかも? 両脚→大腿外旋保ちつつ片脚へ、反対側を挙上
17.5.1.5. 長母趾屈筋ストレッチ 距骨の内側後方移動が制限される
17.5.1.6. ・足部内転エクササイズ:座位 大腿に対して下腿を内旋させる(踵を外側へ、母趾を支点に後足部を動かす) ・足部内転エクササイズ:立位 →立脚期前半で大腿内旋するタイプで行わないように
18. 炎症
18.1. 変形性膝関節症患者における膝の炎症と膝の痛みとの関連性:系統的レビュー
18.1.1. ・関節の炎症徴候(浸出液、滑膜炎、ベーカー嚢胞)および分子炎症因子(血液または滑液中のCRPおよびサイトカイン濃度)が膝OA患者の痛みと関連している ・ベーカー嚢胞と浸出液の間に正の相関あり、293 人の患者 (73.4%) が変形性関節症の超音波検査の特徴を示し、251 人 (62.9%) が関節浸出液を示した ベーカー嚢胞は 102 人の患者 (25.8%) で見つかり、変形性関節症および関節液貯留の超音波検査の特徴との正の関連性が認められた https://www.reumatismo.org/index.php/reuma/article/view/reumatismo.2013.715 ・IL-6 と TNF-α は OA において主要な炎症促進活性を有し、神経支配侵害受容器を活性化する https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25066335/ ・TNF-α血清レベルがOAの重症度に応じて増加する https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27932045/ ・一つの研究40は、滑膜 CRP レベルと痛みとの間に正の関連性があることを発見 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29196131/ 残りの3つの研究は血中のCRPレベルを測定したところ、痛みとの相関関係は見つからなかった https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11350852/ https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26633689/ https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23973128/ ・我々の結果は、サイトカイン濃度が痛みと関連していることを示しているが、抗炎症療法(例、TNFα、IL-1α、またはIL-1βに対処する療法)は臨床症状を軽減しない、また、膝 OA 患者における IL-6 遮断の効果に関する証拠はない https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29499287/ https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17516620/ https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23036475/ https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30653843/ https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30552176/ ・膝OAにおいて疼痛感作の兆候には強力な証拠がある https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30423181/ ・感作を評価するために痛みの実験的測定(定量的感覚検査)を実施した研究は少ない https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26633689/ https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31680799/ https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33907458/ ・画像所見(MRI、超音波)による滑膜炎と疼痛の関連性は中等度
18.1.1.1. ・非造影MRIによる滑膜炎と痛みの関係 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28864651/ ・造影MRIによる滑膜炎と痛みの関係 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20472593/
18.2. 細胞外マトリックスリモデリングのバイオマーカーC1Mと炎症誘発性サイトカインインターロイキン6は、末期変形性膝関節症患者の滑膜炎と痛みに関連している
18.2.1. ・C1M と NPQ の間には関連性が見つかった ・C1M と IL-6 が滑膜炎と痛みに関連しており、OA患者のバイオマーカーと神経障害の特徴を研究する際に滑膜炎が重要な交絡変数であることを示唆
18.3. 変形性膝関節症患者における人工膝関節全置換術後の転帰を予測する代謝因子と炎症マーカーの同定:系統的レビュー
18.3.1. ・IL-1B および TNF-α の末梢血濃度と、TNF-α、MMP-13、IL-6の滑液濃度 が高いことが、術後の痛みの発生の独立した予測因子である これは、炎症促進性サイトカインが末梢神経終末を感作し、術前の末梢および中枢感作を引き起こす可能性があるという事実によって説明できる https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33007930/ https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23157967/ https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25606597/ これは、TKA後の術後疼痛に関連している https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27331347/ ・特定のマイクロRNA(hsa-miR-146a-5p、hsa-miR-145-5p、およびhsa-miR-130b-3p)のレベルが高いと、術後の痛みの軽減が低いことと関連している https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33021154/ 高レベルの TNF-a および IL-1B は hsa-miR-146a-5p の発現を誘導し、この経路が OA の病因に関与している https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24873879/ https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29072705/
18.4. 変形性膝関節症の痛みに関連する滑液中の炎症性メディエーターのプロファイリング
18.4.1. ・K-Lグレードが高いほどIL-1β、IL-6は低い ・炎症性サイトカインと痛みスケールは負の相関 ・K-Lグレードが高いほどROMは小さい ・K-Lグレードが高いほど痛みは強い ・K-Lグレードが高い症例は痛みは強いが、炎症性サイトカインは低いので、重症例の痛みは炎症以外の要因が関わっている可能性が高い
18.5. Nerve growth factor(NGF)
18.5.1. ・種々の炎症性メディエーターによってNGFが産生される ・NGFは主にTrkAを持つC繊維に取り込まれ、後根神経節細胞(DRG)に運ばれ、疼痛増強因子として作用し、疼痛の増悪が生じる ・NGF:神経成長因子→痛みに影響し、神経軸索の伸長、神経伝達物質の合成・促進に関与 TrkA(トラックA)は感覚神経に存在しており、NGFはTrkAと結びつくのでC繊維に取り込まれる
18.6. 滑膜炎のメカニズム
18.6.1. 1軟骨分解時に細胞外マトリックスから関節腔に放出されるDAMPs 2炎症性細胞の浸潤に伴う裏打ち細胞の増殖、過形成と3新生血管の形成 4滑液中への炎症性メディエーターの産生 5炎症性メディエーターが軟骨細胞を活性化し、軟骨細胞がメタプロテアーゼを産生することで悪循環に陥る 6軟骨と滑膜の間に存在 https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmed.2020.607186/full
18.7. パワードップラー超音波信号と人工膝関節全置換術後の慢性疼痛との関連性: 横断的探索的研究
18.7.1. ・膝を15の領域に分けてパワードップラーで評価し、0-3のグレードを割り当てた ・WOMAC疼痛スケールと合計PDスコア、最大PDスコアに正の相関あり ・最大PDスコアよりも合計PDスコアの方が痛みに影響を与える ・手持ち式圧痛計でPD信号が観察された部分の圧痛閾値を計測、PD信号がある部分のPPTはPD信号がない部分のPPTより有意に減少あり
19. 軟骨 (articular cartilage OR cartilage OR subchondral bone) AND knee joint AND pain
19.1. 変形性関節症では、軟骨の減少により痛みが生じますか?また、痛みがある場合、どの程度の痛みが生じますか?
19.1.1. ・軟骨の厚さの減少は、24 か月にわたる痛みのわずかな悪化と有意に関連 ・軟骨厚さの減少と痛みとの関連は、滑膜炎の変化による ・滑膜炎や BML が OA の痛みの原因であることを示すかなりの証拠がある
19.2. 末梢関節変形性関節症における軟骨下骨の特徴、痛み、構造的病理の関係の系統的レビュー
19.2.1. ・変形性関節症では、軟骨下骨リモデリングの恒常性維持プロセスが失敗し、骨の代謝回転、体積、硬さおよび衝撃吸収能力の変化が増 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21864409/ https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12483721/ ・BMLは組織学的に骨代謝回転の増加を表す https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2688243/ ・骨棘はOAに典型的な軟骨下骨肥大を表し、軟骨内および直接骨形成を表し、各膝軟骨プレートの周囲、特にOAの内側で骨面積の円周方向の増加を引き起こす https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24306109/ ・偶発的な骨の減少は、同じコンパートメント内のBMLの存在と強く関連 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2818146/ ・BMLが疼痛を引き起こすメカニズムは不明であるが、軟骨下微小骨折、虚血を引き起こす血液供給の減少による狭心症、骨内圧の上昇などがある可能性がある https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15283450/
19.3. 変形性膝関節症における半月板の病状、軟骨喪失、関節置換術および疼痛の関係:系統的レビュー
19.3.1. ・半月板の押し出しと半月板の断裂は、年齢、性別、BMIとは無関係に軟骨構造の進行と膝関節全置換術の発生率と関連 ・半月板後根修復がOA軟骨喪失のリスクを低下させる https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26493550/ 後根裂傷がOA軟骨進行のリスクを高める理由の1つの可能性は、異常な体重分布、脛骨大腿骨の接触面積の減少、フープ張力の喪失によるピーク接触圧力の増加を引き起こし、硝子関節軟骨の損傷と半月板の押し出しにつながる円周線維の破壊によるもの https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29054695/ https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15067276/ https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26330993/ ・前角と体の押し出しとOA軟骨の進行との間に正の関連 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15374855/
19.4. 変形性関節症における固有受容感覚と機械受容器:系統的文献レビュー
19.4.1. 膝 OA 患者には明確な固有受容不全が存在することを示した
19.5. 石灰化組織の解剖学と生理学:変形性関節症の病因における役割
19.6. 変形性関節症の病因: 分子メカニズムの概説
19.6.1. ・OA の初期段階では、軟骨表面はまだ無傷 細胞外マトリックスの分子組成と構成が最初に変化 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20392241/ 正常な関節では再生能力がほとんどなく、代謝活性も低い関節軟骨細胞は、病理学的刺激によって引き起こされる修復を開始しようとして、一過性の増殖反応とマトリックス合成(Col2、アグリカンなど)の増加を示す 関節軟骨の組成と構造の変化により、軟骨細胞がさらに刺激されて、軟骨の分解に関与する異化因子がさらに生成 プロテオグリカン、そしてコラーゲンのネットワークが破壊されると、軟骨の完全性が破壊 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC128908/ その後、関節軟骨細胞はアポトーシスを起こし、最終的には関節軟骨が完全に失われる 軟骨の完全な喪失により関節空間が減少すると、骨間に摩擦が生じ、痛みや関節の可動性の制限が生じる
19.7. ・OAとは、滑膜関節内の局所的な関節軟骨の損失を特徴とする病態で、骨の肥大(骨棘および軟骨下骨の硬化)および関節包の肥厚を伴った状態 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9588729/ https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21907813/ https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/1529-0131(200109)44:9%3C2065::AID-ART356%3E3.0.CO%3B2-Z ・メカニズムは未解明ではあるが、関節への反復される過度な力学的負荷、経時的かつ累積的な軽度な炎症、またはライフコースの中で損傷によって発症するとされている https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1742706118304318 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27539668/ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4630675/ ・個人レベルの危険因子では、社会人口学的特性(性別や人種など)、遺伝的素因、肥満、食生活、骨密度、関節レベルの危険因子では、特定の骨や関節の形状、筋力低下、関節のアライメント異常、職業やスポーツ活動、既往歴などがある https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29227353/ ・軟骨細胞密度は加齢とともに減少し、コラーゲンなどの新しい繊維の合成が少なくなる。軟骨細胞密度が低下すると、コラーゲンの生産量が減少するため、基質の保護機能が低下し、残存する細胞がさらなる損傷を受けやすくなり、さらに細胞損傷とコラーゲン産生減少が起こるという悪循環が生じる https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25783021/ ・細胞外基質の構造も加齢とともに変化し、関節軟骨の軟化および伸張力を低下させる https://www.ingentaconnect.com/content/ben/cdt/2007/00000008/00000002/art00013 ・コラーゲン繊維の間にある架橋は、しなやかで弾性のある基質を維持しているが、老化産物である産物である終末糖化産物(AGEs)が蓄積されると、分子内に生理的架橋とは別の糖化架橋(老化架橋)を形成し、軟骨の弾性を失わせる https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/art.10627 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11822407/ ・終末糖化産物は特異的レセプターを介して生物学的なシグナルを細胞内に惹起し、例えばこのレセプターが活性化するとさまざまな炎症性サイトカインを誘導することがわかっている https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10399917/
20. 膝蓋腱・膝蓋支帯
20.1. 膝蓋大腿痛の発生率と有病率:体系的レビューとメタ分析
20.1.1. ・膝蓋大腿痛はオーバーユースによる損傷と言われ、短期間のオーバーユースや身体活動の増加は特定の危険因子 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15531059/ https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22031622/ ・初心者ランナーの 10 週間の発生率は、1,000 人年あたり 1080.5 件で、徴兵された軍隊の新兵の発生率と同等 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21632979/ ・報告された発生率が最も高い研究(571.4/1,000人年)は、徴兵制度のある国からのものであり、激しい身体活動に慣れていない参加者からなる集団が含まれている可能性がある https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1874766/ ・短期間の慣れない高レベルの身体活動が膝蓋大腿部痛(PFP)発症の危険因子であるとするモデルと一致しているよう
20.2. 膝蓋大腿関節のどの画像特徴が膝蓋大腿痛に関連していますか? 系統的レビューとメタ分析
21. 予後
21.1. 変形性膝関節症患者における疼痛と身体機能の予後:系統的レビューとメタアナリシス
21.2. 人工膝関節全置換術後の持続性疼痛の予測因子:系統的レビューとメタ分析
21.2.1. ・他の部位の痛み、破局性疼痛と術前疼痛がTKA 集団における慢性術後疼痛の最も強力な独立した予測因子 痛みの複数の部位は、侵害受容系の広範な感作を示唆 ・壊滅的な思考により、術後の痛みに注意が集中し、その認識が高まり、痛みの強度が増大する可能性がある https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11289089/
22. TKA
22.1. CPSP
22.1.1. 慢性疼痛を科学する
22.2. 人工膝関節全置換術後の持続性疼痛の予測因子:系統的レビューとメタ分析
22.3. 人工膝関節全置換術後の痛みと相関する因子:系統的レビューとメタ分析
22.4. 人工膝関節全置換術後の慢性術後疼痛:滑膜炎、疼痛感作、および疼痛の壊滅的寄与の可能性 - 探索的研究
23. 治療
23.1. 変形性膝関節症に対する周術期疼痛管理の実際と有用性
23.2. OA治療の原則 ・力学的負荷量と分散・分布への取り組み →基本的には不可逆的な変化のため、患部の治療経過に応じて治療を進めるのではなく、局所的な負荷を増大させることなく、症状や変形の増悪を防ぐことが1つの目的
23.3. ・OAの疼痛に対して、リハビリではセルフマネジメントプログラム、運動療法、体重減少、認知行動療法、物理療法、杖や装具が推奨 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31652929/ ・力学的ストレスを念頭に置きながら、多面的に原因を探索し、可変的な増悪因子の除去、改善を図る https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31945457/
23.4. ・力学的負荷の軽減 KAMやKFM(膝関節屈曲モーメント)が膝内側関節面の応力を局所的に増大させ、症状の増悪を引き起こす負荷の指標になる KAMを減らす即時的な方法は、杖やインソール、靴、膝装具、歩行修正など(p525、表7) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23756435/ KFMは膝関節屈曲拘縮だけでなく、脊柱後彎や骨盤後傾などの姿勢の退行性変化で増加するとされ、患部以外の介入も重要 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12585585/ 膝OAヘの筋トレはKAMを減少させなかったが、疼痛や臨床成績を改善させる、減量目的としたエクササイズとしても有用であることが示されている https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25896448/ https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18614957/ https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31945457/
24. 運動療法
24.1. 変形性膝関節症患者の痛みと身体機能に対するレジスタンストレーニング投与の役割:系統的レビュー
24.1.1. ・大腿四頭筋の強化はCKCでもOKCでも痛みと身体機能にプラスの効果 ・レジスタンストレーニングの結果と膝OAの場所(内側or外側)、KLグレードとの間に傾向はなかった ・最適な回数、最大強度、介入セットや繰り返しの頻度について、明確な結論を出せなかったが、合計 24 回のレジスタンス トレーニング セッションと 8 ~ 12 週間の期間が、大きな効果量と最も関連していた
24.2. 変形性膝関節症に対する運動トレーニングの効果とメカニズム
24.2.1. KOA の初期段階では、関節軟骨はまだ無傷 しかし、細胞外マトリックスの分子組成と組織が最初に変化し https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20392241/ これにより機械的強度の低下を伴う水結合能力の変化(軟骨軟化症)が生じ、負荷がかかると軟骨の変形が大きくなる https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4481392/ 軟骨損傷の領域では、軟骨下板および関節下海綿体の厚さが徐々に増加し、その生体力学的特性が低下する https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27000393/ KOAの初期段階では、関節軟骨および骨棘の神経支配は、血管および神経によるそれらの侵入と関連 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2111605/ さらに、エストロゲン受容体を介したエストロゲンは、変形性関節症の軟骨分解を媒介し、軟骨喪失の進行を加速 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7809777/ さらに、ホッファ脂肪体は炎症を起こし、大腿四頭筋が弱くなり、膝関節の靱帯が弛緩する https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34465902/ KOA の進行段階では、関節表面とその下にある硝子軟骨の材料特性と構造的完全性が徐々に劣化 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20392241/ 軟骨下骨では、変化には軟骨下板厚の漸進的な増加、軟骨下小柱骨の構造の変化、関節縁での新しい骨の形成が含まれる https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20392241/ 半月板付着部の機械的および構造的変化は、半月板の断裂、剥離、および押し出しに寄与する可能性がある https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3923977/ 膝蓋下脂肪体では、炎症が増強され、IL-1βが増加し、マクロファージが増加し、軟骨変性を悪化させる可能性がある https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21998115/ さらに、関節軟骨の組成および構造の変化は、軟骨細胞をさらに刺激して、軟骨分解に関与する異化因子をより多く産生する https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4747051/ 最も重要な異化因子は、メタロプロテイナーゼの 2 つのファミリー メンバー、マトリックス メタロプロテイナーゼ (MMP) と ADAMTS (ディスインテグリンおよびトロンボスポンジン モチーフを持つメタロプロテアーゼ) これらは、変形性関節症の関節の活性化された軟骨細胞によって生成される細胞外マトリックスの重要な分子であり、関節軟骨の主要成分の分解の原因となる https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC128908/ このプロセスが続くと、異化活性の増加は分解性プロテイナーゼ遺伝子の産生の亢進に関連しており、その結果、プロテオグリカンが徐々に失われ、続いて II 型コラーゲンが分解される可能性がある https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20392241/ その後、軟骨の完全性が破壊され、硝子軟骨の水分含有量が増加する https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22471357/ 関節軟骨細胞はアポトーシスを起こし、最終的には関節軟骨が完全に失われます https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4938009/ 軟骨は摩擦を軽減し、負荷によって下にある骨にかかる力を均等に分散する役割を果たします 軟骨が完全に失われると関節スペースが減少し、その後骨間の摩擦が起こります https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4938009/ KOAの最終段階では、患者には痛み、こわばり、腫れ、関節の可動性の制限などの症状が現れる
24.3. 変性半月板病変に対する関節鏡視下手術または運動療法:系統的レビューの系統的レビュー
24.4. 理学療法士による人工膝関節全置換術の管理
25. 感作
25.1. 変形性膝関節症と疼痛感作
25.2. 変形性膝関節症および股関節症患者における神経因性疼痛および/または疼痛感作の有病率に関する系統的レビューとメタ分析
25.2.1. ・OA患者は罹患関節と非罹患関節の両方において健康な対照よりも疼痛閾値が低い https://www.oarsijournal.com/article/S1063-4584(12)00864-3/fulltext
25.3. 術前の神経障害様の痛みと中枢性感作は、変形性膝関節症に対する膝関節置換術の術後の転帰に影響しますか? 体系的なレビューとメタ分析
25.3.1. ・3件の研究では、術前の神経障害様の痛みまたは感作が術後のより強い痛みと関連していることが示された ・膝関節置換術後の重大な痛みのリスクを調べた 4 つの研究はすべて、3 か月を超えると痛みが増加することを示唆 ・患者の満足度と機能を調査した唯一の研究では、術前感作のある患者では満足度が低下したが、機能には差がなかった ・メタアナリシスでは、神経障害様疼痛(painDETECT ≥13)のある患者における膝関節置換術後の痛み増加の相対リスクは 2.05(95% 信頼区間 1.51、2.79)であることが判明
25.4. 神経因性疼痛: メカニズムとその臨床的意義
25.4.1. ・炎症性メディエーター(プロスタグランジン、ブラジキニンなど)が侵害受容器を興奮させ、発火閾値が低下することで異所性放電が生じる ・持続的な侵害受容刺激はC繊維の活性化と反復的な発火を引き起こし、触覚などに関与する受容体が痛みに反応(二次性痛覚過敏) ・発火の閾値が低下する=痛みを感じやすくなる、異所性放電:侵害刺激がなくても活動電位が生じること 二次性の痛覚過敏=本来痛みを感じないような刺激でも痛みを感じてしまう
25.5. 変形性関節症の疼痛患者における中枢性感作の証拠:体系的な文献レビュー
25.5.1. 膝OA患者の慢性痛には中枢神経系の変容と中枢性感作が影響
25.6. 筋骨格系の痛みにおける中枢性感作:翻訳が失われた?
25.6.1. ・中枢性感作 二次ニューロンの興奮性増大 シナプス伝達の強化 下行性疼痛抑制系の異常 ・中枢神経感作:中枢神経系における,侵害受容ニューロンの正常あるいは閾値以下の求心性入力に対する反応性の増加
25.7. 中枢性感作:痛みの診断と治療への影響
25.8. 変形性膝関節症の女性における痛み、X線撮影の重症度、中枢性症状との関連性
25.8.1. ・痛みの重症度と睡眠障害およびうつ病との間には強い関連性がある ・うつ病と痛みの重症度との関係は、X 線検査の重症度がより高いレベルの人に比べて、X 線検査の重症度が低い人 (ケルグレン・ローレンスグレード 0 ~ 1) の方が強い
25.9. 中央感作インベントリの測定特性: 系統的レビュー
25.9.1. CSI:中枢性感作症候群の評価、中枢性感作に関する症状がどれほど重なり合っているかを評価する指標で、システマティックレビューで十分な信頼性と妥当性があることが報告
25.10. 中央感作目録の短縮形のカットオフ値
25.10.1. CSI-9
25.11. いわきコホート研究から得られた変形性関節症の一般集団における中枢性感作と夜間膝痛有病率の増加との関連性
25.11.1. CSI-9は膝OAの重症度とは関連なかったが、夜間時痛や能力障害、睡眠の質と関連していた
25.12. 痛みなくして成長なし?理学療法における疼痛神経科学教育の視点
25.12.1. 疼痛神経科学の教育:PNE
25.13. 変形性膝関節症に対する膝関節可動化と組み合わせた術前の疼痛神経科学教育:ランダム化比較試験
25.13.1. PNE実施時の10のポイント ①病理解剖学モデルには言及しない ②急性痛 vs 慢性痛(急性痛から慢性痛への移行) ③神経細胞、シナプス、活動電位 ④末梢性感作、中枢性感作 ⑤痛みの下降抑制 ⑥中枢性感作を維持、促進する因子(感情、ストレス、認知など) ⑦脳内における痛みのマトリックス ⑧認知された脅威に対する正常な脳の反応としての痛みの再認識 ⑨神経過敏症に影響を与える手術経験と環境的側面、(再)術後疼痛の概念化 ⑩痛みに関する知識を行動変容に活用
25.14. 慢性筋骨格痛に対する疼痛神経科学教育と運動の組み合わせの短期的影響:体系的レビューとメタ分析
25.14.1. 運動+PNEは運動単独よりも痛み、能力障害、運動恐怖の改善に有効
25.15. 有酸素運動は筋骨格系の痛みを持つ人の痛みの感作に影響しますか? 体系的なレビュー
25.15.1. 有酸素運動により圧痛閾値の増加、疼痛の減少を認めた 種類:ウォーキング、サイクリング 時間:40-60分(最大強度に満たない範囲で段階的に負荷 ↑) 効果:運動開始後2-12週間
26. BML
26.1. varus thrustから見た変形性膝関節症におけるbone marrow lesionsの病態・評価・治療
26.1.1. ・早期膝OAでは侵害受容性疼痛を呈することが多く、その痛みは主に荷重時に生じる https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31034380/ ・膝OAの侵害受容性疼痛には以下が関連する BML https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11281736/ https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17763427/ https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30156085/ 骨棘などの構造的変化、滑膜炎のような炎症性の病態 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21187293/ https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34393106/ 関節軟骨や半月板の神経発現 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29267879/ ・BMLは膝関節への異常なメカニカルストレスが原因 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25634907/ 疼痛を有する膝OAの66.0~77.5%に存在する https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11281736/ https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20823092/ https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31287714/ ・膝のメカニカルストレスを増大させる要因としてvarus thrustが考えられており、この程度がBMLに関与すると考えられる https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28104540/ ・BMLの定義は「構造的なOAを有する関節軟骨に隣接し、目に見える骨折線がないこと」 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36191832/ ・OA-BMLsの特徴はX線上で変形を認める前から発生している点 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33731688/ https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29266428/ 軟骨下骨における微細な構造変化が関節軟骨の変化より先行して生じていることを示唆 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20392241/ 軟骨下骨の構造的変化は関節面の輪郭を変化させ、さらなるメカニカルストレスの要因にもなるため、膝OAの進行にも影響する可能性がある https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36191832/ ・BMLのサイズと疼痛強度に影響あり、BMLの有無だけではなくサイズも重要 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30156085/ ・人工膝関節置換術を施行した患者から術中に骨組織を採取し病理学的所見とMRI所見を比較したところ、BMLが生じていた場所には骨嚢胞、軟骨下繊維症、血管の過剰分布、骨内の新しい軟骨を示す軟骨島、海綿状肥厚、tidemark integrityの喪失、炎症性細胞の浸潤が観察された。これらの所見は神経成長因子(NGF)の発現と関連が報告されている https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35124198/ https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20581375/ NGFはサブスタンスPやセロトニンの発現を仲介し、広範な痛覚過敏を誘発する https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21737902/ https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0021925818824152 ・varsu thrustは膝OAの12-46%に観察され、内側脛骨大腿関節に異常なメカニカルストレスを与える https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23948980/ https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26089038/ https://acrjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/acr.22558 ・内側脛骨大腿関節におけるメカニカルストレスの指標は外部膝関節内転モーメント(KAM)が使用される https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19321348/ https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25795547/ https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24725590/ ・varus thrustの程度とKAMは相関関係あり https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21300549/ ・BMLはMRI上の構造的な特徴を半定量化するツールであるMOAKSが主に用いられる https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21645627/ ・PFJのBMLに対してPFブレースを6週間装着する装具療法を実施後、膝痛の軽減、BMLの縮小を認めたが、脛骨大腿関節のBMLには効果がなかった →どの部位のBMLなのかを確認して、それに適した装具を選定する必要あり https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25596158/ ・varsu thrustの抑制には外側ウェッジインソールの使用でKAMや疼痛を軽減する効果が報告されている https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35140149/ https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30030612/ 一方、OAの重症度やアウトカム測定方法の違いで使用しても効果がなかったという報告もある https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25773267/ https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25467955/ https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21593096/
26.2. 変形性膝関節症患者における軟骨下骨髄病変の局在化と体重負荷時の痛みとの関連: 変形性膝関節症イニシアチブのデータ
26.2.1. 膝OAではBMLと滑膜炎、水腫が重要な疼痛源である
26.3. 変形性膝関節症における骨髄浮腫パターン:MR画像と組織学的所見との相関
26.3.1. 骨髄浮腫はリモデリングや微小骨折による骨髄内炎症や浮腫を描出していると考えられているが、組織学的には浮腫だけではなく、繊維化や骨壊死の所見も確認されており、現在では広くBMLとして呼称されている
27. PCL
27.1. ・OA が悪化すると、炎症因子の侵入と時間の経過による物理的磨耗により PCL が徐々に変性 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10464102/ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10475681/ ・組織学的変性が進行するにつれて、PCL の神経血管構造がより大きな損傷を受ける https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4351312/ ・PCLは固有受容と筋肉の関与を通じて膝関節の動的安定性に大きく貢献 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8870829/ ・Golgi Corpuscles、Ruffini Corpuscles、自由神経終末、総神経終末、およびPCLの小さな血管の数は、OA患者の患者では低い https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1063458413000435?via%3Dihub https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4626232/ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3940730/ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7457474/ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10273789/ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4351312/ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10324928/ ・PCLメカノレセプターの数がWOMACスコアの増加(膝OAの重症度の尺度)とともに減少した https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7457474/ ・動的安定度測定を使用すると、膝の単独の関節軟骨病変を持つ患者でも重大な固有受容欠損が検出され、関節軟骨病変も膝の固有受容機能に大きな影響を与えていることが示された https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7457474/
27.1.1. 変形性膝関節症におけるMRIを用いた膝関節固有受容の低下と内側半月板異常との関連性:アムステルダム変形性関節症コホートの結果
27.1.1.1. ・膝OAでは、固有受容の精度が低下し、痛みや活動の制限に関連する可能性があります 固有受容精度の低下の原因は多岐にわたりますが、膝OA でよく見られる内側半月板の異常が重要な役割を果たしていることが示唆
