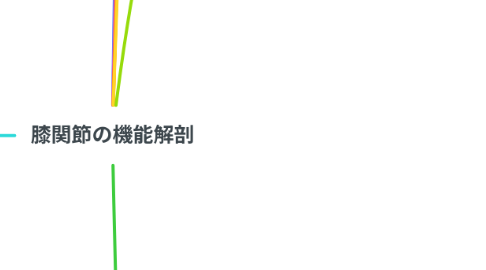
1. 膝関節の関節運動に関わる要因は ①大腿骨と脛骨の形態 ②靱帯、関節半月、関節包などの静的安定化機構 ③筋による動的安定化機構
1.1. ・膝関節は、体重を支持するための安定性、歩行や走行に必要な可動性が要求される。 ・膝関節は、骨性の安定性に乏しく、覆っている軟部組織が少ないが、可動性が大きく荷重負荷も大きい。 ・安定性のほとんどは靱帯、関節半月、筋を中心とした軟部組織に依存している。
2. 膝関節を構成する骨は?
2.1. 大腿骨
2.1.1. 頸体角 正常:約125°
2.1.1.1. 頸体角があるため、わずかに内側方向に曲がりながら膝関節まで伸びる。
2.1.1.2. 脛骨近位関節面はほぼ水平なので、膝関節では170°〜175°の角度をなす。 これを大腿脛骨角=FTA
2.1.1.2.1. FTA ①正常:170〜175° ②170°以下:外反膝(X脚) ③180°以上:内反膝(O脚)
2.1.2. ・形態的には外側顆の方が大きいが、関節面は内側顆の方が広い。 ・形状、大きさ、曲率が大きく異なります。内側顆は外側顆に比べて関節面が大きく、 前後方向に湾曲した表面を特徴としており、膝の回旋運動において重要な役割を果たします。 この湾曲は、大腿骨と脛骨の内旋と外旋に不可欠であり、スクリューホームメカニズムと呼ばれる膝関節のロック機構とロック解除機構に寄与しています。 対照的に、外側顆は表面積が小さく、曲率半径が異なるため、膝の屈曲時に異なる運動学的挙動が生じる。 ・内側顆および外側顆の側面で後1/3ほどのところが突出しており、これを内側上顆、外側上顆とよぶ。 ・内側上顆の位置は外側上顆に比べ、後方かつ上方に位置している。そのため、両者を結んだ線は水平面に対し平行にならない。
2.2. 脛骨
2.2.1. 脛骨の主な機能は、膝関節を超えて足関節へ荷重を伝達すること
2.2.2. 大腿直筋の長軸および膝蓋骨の中心と脛骨粗面を結ぶ線の交差する角度はQ角(Q -angle)と呼ばれる。 これは、膝蓋骨脱臼をはじめとする膝蓋大腿関節の安定性の指標として用いられる。
2.2.2.1. ・脛骨粗面の外側偏位は結果的にQ角の増大を招き、膝蓋骨脱臼の危険因子となる ・Q角を観察する際は、臥位時のQ角と立位時のQ角を比較することで、下肢アライメントがQ角に影響するか評価することができる。
2.2.3. 脛骨粗面の近位外側へと伸びる斜線の近位にはGerdy(ガーディー)結節があり、ここには腸脛靭帯が停止する。
2.2.4. 脛骨の関節面は、内側は平面か若干凹の形態を呈しているため、大腿骨顆部との適合性は凹凸の関係で適合が良い。 適合性が良いため、可動性は小さい 外側は、平面か若干の凸の形態を呈しており、しかも後方に向かって傾斜しているため、大腿骨顆部との適合性は不安定。 適合性が不安定なため、可動性は大きい。
2.3. 膝蓋骨
2.3.1. ・膝蓋骨の上端を膝蓋骨底、下端が尖っており膝蓋骨尖とよぶ。 ・大腿四頭筋・膝蓋靱帯とともに膝関節伸展機構を構成。 ・膝関節伸展位では、膝蓋骨の下端が膝関節裂隙にほぼ一致する。 ・膝蓋骨の長径と膝蓋骨尖から脛骨粗面までの長さはほぼ1:1である。 ・膝を屈曲するほど側方動揺が減少する。これは屈曲に伴い膝蓋骨は遠位へ滑り、膝蓋骨との適合性が高まるためである。
2.3.2. 3つの機能を有する
2.3.2.1. ①前方からの圧力や衝撃に対して関節を保護する。 ②伸展機構の滑りを可能にする。脛骨大腿関節の屈曲・伸展に追従して、膝蓋骨は大腿骨の顆部関節面の中心を滑る。 ③作用軸を修正し、大腿四頭筋に効率を高める。
2.3.2.1.1. 伸展機構としての膝蓋骨の存在は、膝蓋腱の中枢部分を回転中心から遠ざけ、牽引力の作用モーメントを増大させる。 →大腿四頭筋のレバーアアームを延長し、伸展力の効率化に寄与する。
2.4. 腓骨
2.4.1. 膝関節の形成に直接には関与はしないが、膝関節に関与する靱帯や筋の付着部となっている点で重要
2.4.1.1. 脛骨を外側で支え、骨配列を維持する助けとなっている
2.4.2. 腓骨頭は大腿二頭筋と外側側副靱帯の付着部
3. 膝関節の細分化
3.1. 脛骨大腿関節(FT関節)
3.1.1. ①関節頭である大腿骨の外側顆と内側顆は比較的強い凸をなす、 関節窩である脛骨の外側顆と内側顆は平坦である
3.1.1.1. 大腿骨と脛骨間の適合性を高めるために繊維軟骨性の関節半月が存在する
3.1.1.2. 脛骨の外側関節面は平坦かわずかに凸形状のため、外側の関節半月は重要
3.1.2. ②大腿骨顆部と脛骨顆部の関節面の大きさが異なる
3.1.3. ③大腿骨内側顆と外側顆では関節面の大きさが異なる
3.1.4. ④内側・外側の関節面において前後の曲率半径が異なる
3.1.4.1. 曲率半径 ・関節面の曲率のことであり、同じ曲率をもつ縁の半径の長さ ・表面が湾曲するほど曲率半径は小さい ・類似した曲率半径をもつ関節面は適合しており、骨の安定性が高い
3.2. 膝蓋大腿関節(PF関節)
3.2.1. 役割:膝関節伸展筋力の効率を高める
4. 関節半月(半月板)
4.1. 内側および外側の脛骨関節面の辺縁部を覆う繊維軟骨
4.1.1. 役割 ①荷重の分散・吸収
4.1.1.1. 関節半月には粘弾性があり、長時間の圧縮力に対して、負荷を受ける面積を拡大し圧力の軽減を図り、関節半月実質内の水の再配合による負荷緩和現象にて応力を吸収する
4.1.2. ②関節半月の辺縁部が楔状に厚くなっているため、脛骨大腿関節の安定性増大
4.1.2.1. 外縁が厚く、内縁ほど薄い構造をしており、大腿骨顆部に適合して安定性に寄与している
4.1.3. ③滑液による潤滑膜を2重にすることができ、より摩擦の軽減に寄与する
4.1.4. ④関節軟骨の潤滑
4.1.5. ⑤固有受容感覚の供給
4.1.6. ⑥関節包内運動の誘導を補助
4.2. 曲率半径が大きくC型の内側半月、 曲率半径が小さくO型の外側半月からなる。
4.2.1. 内側半月は関節包を介して内側側副靱帯に付着している
4.2.1.1. MCLに付着しているため、外側半月より可動性が少なく、損傷の頻度が高い
4.2.2. 外側半月は、外側側副靱帯に付着していない
4.3. 内側半月は、前方から後方まで関節包に付着している。 前角と後角の付着部が離れている。 外側半月は、前方の半分ほどが関節包と連結しており、後方は連結していない。 前角と後角の付着部が近い。
4.3.1. このような構造的特徴から、内側半月よりも外側半月は可動範囲は大きい。
4.4. 関節半月は、屈伸・回旋に伴い、大腿骨顆部と同じ方向に移動する。 屈曲時:脛骨に対する大腿骨顆部の後退により半月板も後方に移動。 伸展時:脛骨に対する大腿骨顆部の前方移動により半月板も前方に移動。 内旋時:内側半月は前方へ移動し、外側半月は後方へ移動。 外旋時:内側半月は後方へ移動し、外側半月は前方へ移動。
5. 関節包
5.1. 前面は、大腿四頭筋・膝蓋骨・膝蓋靱帯によって補強される
5.2. 内側面・外側面は、内側側副靱帯・外側側副靱帯によって補強されている
6. 膝蓋上嚢
6.1. ・大腿骨と大腿四頭筋腱の間にある約6−8㎝程度の滑液包 ・大腿骨顆部と膝蓋骨をつなぐ滑液包であり、膝蓋大腿関節の滑動性の効率化に寄与している。
6.1.1. 膝関節伸展時は2重構造になっていて、屈曲時に膝蓋骨下方へ滑って形を変える
7. 膝蓋下脂肪体
7.1. 役割 ・衝撃吸収 ・滑液の分泌 ・膝蓋腱やACLへの血液供給 ・滑走性の促進
8. 膝関節の靱帯は?
8.1. 靱帯は関節の安定性を保持するとともに関節運動を制限あるいは誘導する役割がある
8.1.1. 関節外靱帯
8.1.1.1. 内側側副靱帯(MCL)
8.1.1.1.1. ・膝関節の内側を補強し、大腿骨内側上顆から斜め前方へ走行し、脛骨内側顆の内側縁と後縁に幅広く停止する。 ・浅層と深層に分けられ、深層は内側半月の中節に強く結合している。 ・下腿の外反と外旋を強く制動し、前方引き出しにも補助的に拮抗する。 ・膝関節の外反ストレスに対する抑制力の60〜80%をになっている ・膝関節伸展位で緊張し、屈曲位でやや弛緩する。(屈曲角度が増加してもある程度の緊張は保たれる)
8.1.1.1.2. MCL浅層
8.1.1.1.3. MCL深層
8.1.1.2. 外側側副靱帯(LCL)
8.1.1.2.1. ・膝関節の外側を補強し、大腿骨外側上顆から斜め後方へ走行し、腓骨頭に停止する。 ・内側側副靱帯と違い、円柱状の靭帯で太さは5〜7mm程度である。 ・外側側副靭帯と外側半月には繊維性の結合はない。 ・外側側副靱帯は前方から後方へ走行し、屈伸軸の後方に位置することから内反・外旋・伸展で緊張する。 ・膝関節の後外側を支持する弓状靱帯とともには外側の不安定性を抑制する。 ・伸展位で緊張し、屈曲位で弛緩する。
8.1.1.3. 側副靱帯の主な機能は前額面における過度な脛骨大腿関節の制限である
8.1.1.4. 完全伸展位ではMCL・LCLが緊張するため、内反および外反ストレスで動揺が生じた場合は側副靭帯損傷が考えられる
8.1.2. 関節内靱帯
8.1.2.1. 前十字靭帯(ACL)
8.1.2.1.1. 脛骨の前顆間区から出て、上後方に向かい、大腿骨外側顆の内側面後部に付着し、脛骨の前方滑脱を防いでいる。 (大腿骨外側顆の後内側から脛骨の内側顆間結節の前外側へ走行している。)
8.1.2.1.2. 前内側繊維束(AMB)
8.1.2.1.3. 後外側繊維束(PLB)
8.1.2.1.4. ・主な機能的役割は荷重時の回旋制動である。 ・これに加えて脛骨の前方制動、内旋、外反、過伸展の制動、膝関節の転がりや滑り運動に関与
8.1.2.2. 後十字靭帯(PCL)
8.1.2.2.1. 脛骨の後顆間区から出て、前十字靭帯の内側を前上方に向かい、大腿骨内側顆の外側面前部に付着し、脛骨の後方滑脱を防いでいる
8.1.2.2.2. 前外側繊維(ALB) 靱帯の大部分を形成
8.1.2.2.3. 後内側繊維(PMB)
8.1.2.2.4. ・脛骨の他動的後方移動に対する全抵抗力の95%をPCLが担っている。 ・すなわち、固定された脛骨上で大腿骨前方推進の制動を担っている。 ・PCLの制動により脛骨上で大腿骨を後方に引き込むことで膝屈曲時の後方インピンジメントを回避している。これを膝関節のロールバック機構という。
8.1.2.3. 十字靭帯は関節包内運動の誘導を補助する。 また、走行が矢状面に近いため、膝関節の前後方向の安定性に寄与する
8.1.2.4. 膝関節の内旋でACL・PCLが交差することで受動的に安定する。 歩行時のLRでは大腿骨に対して脛骨が内旋することで安定性を得ている。
8.1.2.4.1. 下腿の内旋では、膝十字靭帯は互いの巻き付いて過剰な内旋を防ぐ。 外旋では、膝十字靭帯はよりほぐれる。
8.1.3. 関節包内靱帯であるACL・PCL損傷時の自己修復困難。 関節包外靱帯であるMCL・LCLは自己修復可能。
8.1.4. その他の靱帯
8.1.4.1. ファベラ腓骨靱帯
8.1.4.1.1. ・膝関節の後外側角を構成する。 ・膝関節後外側にある種子骨であるファベラから腓骨頭の後縁の走行している。 ・膝関節の伸展と外旋で緊張する。
8.1.4.2. 膝蓋靱帯
8.1.4.2.1. ・大腿四頭筋腱の続きで、膝蓋骨下部から脛骨粗面に付く強靭な繊維束。 ・大腿四頭筋の収縮力を膝蓋骨を介して脛骨へ伝える張力伝達装置。
8.1.4.3. 膝蓋支帯(膝蓋骨・膝蓋靱帯の両側にある内・外側広筋へと続く膜様の繊維束)
8.1.4.3.1. 内側膝蓋支帯
8.1.4.3.2. 外側膝蓋支帯
8.1.4.4. 腸脛靱帯
8.1.4.4.1. ・近位は大腿筋膜張筋・大殿筋に繋がり、遠位は脛骨上端の前外側(Gerdy結節)に付着する。 ・脛骨付着部付近では、繊維の一部が外側膝蓋支帯へと侵入し、膝蓋骨の安定化にも寄与する。 ・股関節の内転で緊張、外転で弛緩する。 ・膝関節の伸展により後方部が緊張、屈曲により前方部が緊張する。90°〜100°を超えて屈曲すると、全体として弛緩する。 ・腸脛靱帯は股関節の側方安定性とともに、膝関節の前内側方向の安定性にみ関与する重要なstabilizerである。
9. 膝関節に関係する筋は?
9.1. 筋は動的安定性機構を司る
9.1.1. 主動作筋と拮抗筋が同時に静止性収縮し、関節を固定して支持性を与える
9.1.2. 大腿四頭筋・ハムストリングス・薄筋・縫工筋・腓腹筋の作用方向は大腿骨と脛骨の長軸方向とほぼ並行に走行する。 立位においてこれらの筋は収縮によって膝関節の圧縮力を生じさせ、膝関節の安定性に貢献する
9.2. 大腿四頭筋
9.2.1. 大腿神経に支配される、膝関節の唯一の伸展筋群
9.2.1.1. たった一つの末梢神経に支配されるため、大腿神経損傷は膝関節伸筋に対して大きな問題となる
9.2.2. 膝関節伸展トルクのうち、約80%を広筋群、約20%を大腿直筋が担っている
9.2.3. 大腿直筋 (RF:Rectus Femoris)
9.2.3.1. 起始:下前腸骨棘(ASIS)寛骨臼上縁 停止:膝蓋骨(膝蓋靭帯を介して脛骨粗面へ付着) 神経支配:大腿神経(L2〜L4)
9.2.3.1.1. 作用: ・膝関節の伸展 ・股関節の屈曲(唯一の二関節筋であり、大腿四頭筋の中で股関節屈曲に関与) ・下腿の回旋や股関節の内転・外転にはほぼ関与しない
9.2.3.2. 起始部は直頭・反回頭・third headの3つある!
9.2.3.2.1. ・直頭:下前腸骨棘(AIIS)が起始部 ・半回頭:寛骨臼上縁が起始部 ・third head:大転子の前外側面が起始の繊維で、小殿筋の腱と腸骨大腿靱帯に付着
9.2.4. 内側広筋 (VM:Vastus Medialis)
9.2.4.1. 起始:大腿骨粗線内側唇、転子間線の遠位部 停止:膝蓋骨および脛骨粗面(膝蓋靭帯を介する) 神経支配:大腿神経(L2〜L3)
9.2.4.1.1. 作用: ・主に膝関節の伸展に関与 ・膝蓋骨の安定化(特に膝蓋骨の内側への保持) ・終末伸展機能(膝伸展の最終15〜20度で重要な役割を果たす)
9.2.4.2. 内側広筋縦走繊維(VML)
9.2.4.2.1. 大腿四頭筋腱より内側、膝蓋骨に15〜18°の角度で付着。 膝関節の伸展を主に担う。
9.2.4.3. 内側広筋斜走繊維(VMO)
9.2.4.3.1. 起始:大内転筋腱 停止:膝蓋骨内側縁や内側膝蓋支帯に約50°の角度で付着
9.2.5. 外側広筋 (VL:Vastus Lateralis)
9.2.5.1. 起始:大腿骨転子間線、大転子の外側面、大腿骨粗線外側唇 停止:膝蓋骨および脛骨粗面(膝蓋靭帯を介する) 神経支配:大腿神経(L3〜L4)
9.2.5.1.1. 作用: ・膝関節の伸展 ・膝蓋骨の安定化 ・走行上、下腿の外旋、外転作用を有している
9.2.5.2. 外側広筋斜走繊維(VLO)
9.2.5.2.1. 起始:腸脛靱帯の裏面 停止:膝蓋骨外側縁・外側膝蓋支帯
9.2.5.3. 特徴 ・大腿四頭筋の中で最も大きな筋肉。 ・多くの範囲を腸脛靱帯に覆われている。 ・外側広筋遠位の深部にある繊維は、膝伸展に伴い前方へ、屈曲に伴い後方へ大きく移動する。 ・膝関節の伸展作用とともに、膝蓋骨への外方牽引作用が大きい。
9.2.6. 中間広筋 (VI:Vastus Intermedius)
9.2.6.1. 起始:大腿骨近位2/3 停止:膝蓋骨を介して脛骨粗面 神経支配:大腿神経(L2〜L4)
9.2.6.1.1. 作用: 膝関節の伸展 他の広筋(内側広筋・外側広筋)と異なり、膝蓋骨の安定化に関与する作用は少ない。
9.2.6.2. 特徴 ・大腿四頭筋の最も深層に位置する。 ・膝蓋上嚢に付着している。そのため、膝関節伸展時に、膝蓋上嚢を上方にひっぱり、挟み込みを防止する役割がある
9.3. ハムストリングス
9.3.1. 半腱様筋 (ST:Semitendinosus)
9.3.1.1. 起始:坐骨結節 停止:脛骨粗面の内側(鵞足部) 神経支配:坐骨神経の脛骨神経部 (L4~S2)
9.3.1.1.1. 作用: 股関節の伸展、内転にも補助的に作用 膝関節の屈曲 下腿の内旋(半膜様筋に比べ内旋作用が強い)
9.3.1.2. 特徴 ・半膜様筋の上層を走行し、細長い腱を持つ(遠位1/2が腱)。 ・鵞足(Pes Anserinus)を構成。 ・薄筋・縫工筋とともに、脛骨内側に付着し膝の安定性に関与。 ・歩行の踵接地時に生じる股関節屈曲モーメントを制動し、体幹の直立位保持に役立つ。
9.3.2. 半膜様筋 (SM:Semimembranosus)
9.3.2.1. 起始:坐骨結節 停止:脛骨内側顆、斜膝窩靱帯、膝窩筋の筋膜、膝後方関節包、後斜靱帯、内側半月板 神経支配:坐骨神経の脛骨神経部(L4〜S2)
9.3.2.1.1. 作用: 股関節の伸展、内転にも補助的に作用 膝関節の屈曲 下腿の内旋
9.3.2.2. 特徴 ・半腱様筋の深層に位置し、近位1/2が広い腱膜で構成。 ・膝関節屈曲時の内側半月や後方関節包の挟み込みを防止し、円滑な屈曲運動を誘導している。 ・脛骨の後方引き込みをサポートし、前十字靭帯の負担を軽減。 ・歩行の踵接地時に生じる股関節屈曲モーメントを制動し、体幹の直立位保持に役立つ。
9.3.3. 大腿二頭筋 (BF:Biceps Femoris)
9.3.3.1. 大腿二頭筋長頭 (BFLH:Biceps Femoris Long Head)
9.3.3.1.1. 起始:坐骨結節 停止:腓骨頭 神経支配:坐骨神経の脛骨神経部(L5〜S2)
9.3.3.2. 大腿二頭筋短頭 (BFSH:Biceps Femoris Short Head)
9.3.3.2.1. 起始:大腿骨粗線外側唇 停止:長頭腱を介して腓骨頭 神経支配:坐骨神経の腓骨神経部(S1〜S2)
9.3.3.2.2. 表層は長頭によりほぼ覆われていおり、体表からは長頭の筋腹が主に確認される
9.3.3.3. 特徴 ・大腿二頭筋の停止の一部は、腓腹筋外側頭の筋膜と合流し、腓腹筋外側頭の筋活動に影響を与える。 ・停止腱の一部は、外側側副靱帯を内側・外側より覆いながら腓骨頭へと向かい、間接的に膝関節の内反不安定性を制動する。
9.4. 大腿筋膜張筋 (TFL:Tensor Fasciae Latae)
9.4.1. 起始:上前腸骨棘(ASIS) 停止:腸脛靱帯を介して脛骨粗面に外側にあるGerdy結節 神経支配:上殿神経(L4〜S1)
9.4.1.1. 作用: 股関節屈曲、外転、内旋 膝関節屈曲90°未満では膝関節伸展運動 膝関節屈曲90°以上では膝関節屈曲運動 下腿の外旋
9.4.2. 特徴 ・腸脛靱帯に緊張度を調節し、間接的に膝関節の安定化に関与する。 ・中殿筋、小殿筋とともに、片脚立位時の骨盤の安定化に関与する。
9.5. 縫工筋 (Sart:Sartorius)
9.5.1. 起始:上前腸骨棘(ASIS) 停止:脛骨粗面の内側(鵞足部) 神経支配:L2〜L3
9.5.1.1. 作用: 股関節の屈曲、外転、外旋 膝関節の屈曲 下腿の内旋
9.5.2. 特徴 ・停止部付近では薄筋、半腱様筋とともに鵞足を形成し、膝関節の安定に関与する。 →過度なknee in が強制される動作では、下腿の外旋強制力に拮抗するように、鵞足筋群が働き、動的安定化を図る。 ・縫工筋は薄筋、半腱様筋に比べ、停止部付近まで筋が存在している。
9.6. 薄筋 (Grac:Gracilis)
9.6.1. 起始:恥骨結合の外側 停止:脛骨粗面の内側(鵞足部) 神経支配:閉鎖神経(L2〜L3)
9.6.1.1. 作用: 股関節の屈曲・内転 膝関節の屈曲 下腿の内旋
9.6.2. 特徴 ・大腿の最も内側を走行。 ・薄筋腱は股関節周囲レベルでは縫工筋の深部に滑り込むように走行。
9.7. 膝窩筋 (PM:Popliteus mascle)
9.7.1. 起始:大腿骨外側上顆の外側面 停止:ヒラメ筋線より上の脛骨上面部 神経支配:脛骨神経(L4〜S1)
9.7.1.1. 作用: 膝関節の屈曲 下腿の内旋
9.7.2. 特徴 ・膝窩筋の筋腹には半膜様筋が一部合流してくる。 ・膝窩筋筋腹の直上を、膝窩動脈、静脈が縦走する。 ・膝窩筋の起始の一部は外側半月に付着している。 ・膝関節の屈曲とともに外そく半月を後方へ引き、顆部との挟み込みを防止する。 ・膝関節完全伸展において生じている外旋固定のロックを外す役割がある。
9.8. 腓腹筋 (Gas/GM:Gastrocnemius)
9.8.1. 内側頭
9.8.1.1. 起始:大腿骨内側上顆 停止:踵骨隆起 神経支配:脛骨神経(L4〜S2)
9.8.1.1.1. 作用: 膝関節の屈曲 足関節の底屈
9.8.2. 外側頭
9.8.2.1. 起始:大腿骨外側上顆 停止:踵骨隆起 神経支配:脛骨神経(L4〜S2)
9.8.3. 特徴 ・腓腹筋に筋腹は外側頭に比べて内側頭で発達をしている。 →これは、立位時に加わる膝関節外反ストレスや足部回内ストレスに抗するための変化と考えられている。
