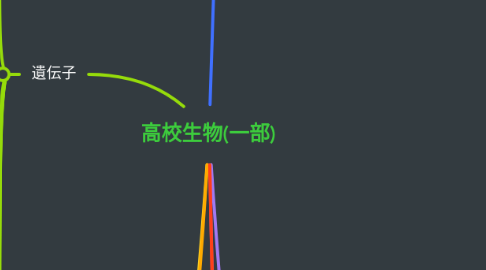
1. 遺伝子
1.1. DNA
1.1.1. 複製
1.1.1.1. 半保存的複製
1.1.1.1.1. なぜ半なのか?
1.1.1.1.2. メセルソンとスタールの実験によって証明
1.1.1.2. ヌクレオチド鎖
1.1.1.2.1. DNAポリメラーゼがくっつき
1.1.2. 二重らせん構造
1.1.2.1. 3´末端から結合していく
1.1.2.2. 染色体
1.1.2.2.1. クロマチン繊維
1.1.3. 材料
1.1.3.1. ヌクレオチド
1.1.3.1.1. リン酸
1.1.3.1.2. デオキシリボース
1.1.3.1.3. 塩基
1.1.4. 研究者
1.1.4.1. グリフィス
1.1.4.1.1. 形質転換を確認
1.1.4.2. エイブリー
1.1.4.2.1. 形質転換の原因がDNAと特定
1.1.4.3. ハーシー&チェイス
1.1.4.3.1. 遺伝子の本体をDNAと特定した!!!
1.1.4.4. ワトソン&クリック
1.1.4.4.1. DNAは二重らせんしてる!!!!
1.1.4.5. シャルガフ
1.1.4.5.1. 塩基の相補性を確認、AとT、GとCの量が同じと確認
1.2. RNA
1.2.1. 一本鎖
1.2.1.1. ヌクレオチドが並んで重なったもの
1.2.2. mRNA
1.2.2.1. 遺伝子発現で使うヤツ
1.2.3. tRNA
1.2.3.1. 運ぶ奴
1.2.4. rRNA
1.2.4.1. リボソームRNA
1.2.5. RNAワールド仮設
1.2.5.1. DNAよりRNAが最初にできた
1.2.5.1.1. 正しいかどうかは怪しい
1.3. 遺伝子発現
1.3.1. セントラルドグマ
1.3.1.1. 転写
1.3.1.1.1. RNAポリメラーゼがくっつきmRNAをつくる
1.3.1.1.2. イントロン
1.3.1.1.3. エキソン
1.3.1.1.4. 核膜内
1.3.1.2. 翻訳
1.3.1.2.1. mRNAの塩基配列に応じたアミノ酸をtRNAが持ってきペプチド結合をする
1.3.1.2.2. 細胞質
1.3.2. 原核生物の遺伝子発現
1.3.2.1. 真核と違う点
1.3.2.1.1. 開裂がない
1.3.2.2. 同じ点
1.3.2.2.1. RNAポリメラーゼを用いる
1.3.2.3. RNAポリメラーゼ
1.3.2.3.1. 3´→5´
1.3.2.4. リボソーム
1.3.2.4.1. 5´→3´
1.3.3. ビートルとテイタム
1.3.3.1. 一遺伝子一酵素説
1.3.3.1.1. 今では否定されているが有力な説
1.3.4. 遺伝暗号
1.3.4.1. 塩基配列を用いた暗号、応じたアミノ酸を持ってくる
1.3.4.2. ニーレンバーグ
1.3.4.2.1. UUU-フェニルアラニン
1.3.4.3. コラーナ
1.3.4.3.1. いっぱい
1.3.4.4. コドンは64通り
1.3.4.4.1. アミノ酸は21種類
1.3.4.5. 開始コドン
1.3.4.5.1. AUG
1.3.4.6. 終止コドン
1.3.4.6.1. UAA
1.3.5. 遺伝子発現の調節
1.3.5.1. 原核生物上
1.3.5.1.1. 遺伝子発現、つまりDNA→mRNAを作るときにこれらがおこる
1.3.5.1.2. 調節遺伝子
1.3.5.1.3. プロモーター
1.3.5.1.4. オペレーター
1.3.5.1.5. 構造遺伝子群
1.3.5.1.6. ラクトースオペロン
1.3.5.1.7. トリプトファンオペロン
1.3.5.2. 真核生物上
1.3.5.2.1. 原核生物との違い
1.3.5.2.2. パフ
1.4. 変異
1.4.1. 環境変異
1.4.2. 突然変異
1.4.2.1. 染色体突然変異
1.4.2.1.1. 構造の変化
1.4.2.1.2. 数の変化
1.4.2.2. 遺伝子突然変異
1.4.2.2.1. 塩基配列の変異
1.4.2.2.2. 置換
1.4.2.2.3. 欠如、付加
1.4.2.2.4. 至高の暗号
1.5. 遺伝子組み換え
1.5.1. 材料(使う順)
1.5.1.1. 逆転写酵素
1.5.1.1.1. mRNA
1.5.2. 1、逆転写酵素を用いmRNAから相補的な一本鎖のDNAを作る
1.5.3. 2、DNAポリメラーゼを用い二本鎖にする
1.5.4. 3、特定の塩基配列を切る
1.5.5. 4、大腸菌の塩基配列から同じ塩基配列を切る
1.5.6. 5、お互いの切り取られた塩基をDNAリガーゼを用いて合体させる
1.5.7. 6、出来た塩基を大腸菌に戻ししてもらいたいことをする
1.5.7.1. 遺伝子組み換えによって、遺伝子の形質を変化させることを「形質転換」という
1.5.8. PCR法
1.5.8.1. 材料
1.5.8.1.1. 目的のDNA
1.5.8.2. 1、95℃に熱しDNA二本鎖の水素結合を外し一本鎖に
1.5.8.2.1. 暑いよ!!!!!!!
1.5.8.3. 2、約55℃に下げプライマーを結合させる(足がかりをつくる)
1.5.8.3.1. DNAポリメラーゼは5→3へ動くのでプライイマーの先が3になるようにする
1.5.8.4. 3、約72℃下でDNAポリメラーゼが周りの塩基を使いプライマーを伸ばして(付加して)いく
1.6. バイオテクノロジー
1.6.1. クローン
1.6.1.1. 受精卵クローン
1.6.1.1.1. 成功確率高い
1.6.1.1.2. 発生初期の細胞をとってきて徐核した細胞につっこむ
1.6.1.2. 体細胞クローン
1.6.1.2.1. 成功確率ひっくい
1.6.1.2.2. ガードンの実験
1.6.1.2.3. 羊ドリー
1.6.2. 幹細胞
1.6.2.1. 色々な種類に分化でき成長能力が高い
1.6.2.2. ES細胞
1.6.2.2.1. :led_red: 胚性幹細胞とも言う
1.6.2.3. IPS細胞
1.6.2.3.1. 人工多能性幹細胞とも言う
1.6.3. キメラ
1.6.3.1. 異なる遺伝的組成の細胞が一個体内の混在していること
2. 生き物の身体
2.1. 生命の階層性
2.1.1. 大きい順
2.1.1.1. 生態系
2.1.1.1.1. 生物群集
2.2. 細胞
2.2.1. 細胞説
2.2.1.1. シュライデン
2.2.1.1.1. 植物の身体の細胞説を提唱
2.2.1.2. シュワン
2.2.1.2.1. 動物の身体の細胞説を提唱
2.2.1.3. 生命の構造と機能の基本単位は細胞であるとするもの
2.2.2. 細胞の研究
2.2.2.1. ロバートフック
2.2.2.1.1. 細胞壁の観察
2.2.2.2. レーウェンフック
2.2.2.2.1. 生細胞の観察
2.2.2.3. ブラウン
2.2.2.3.1. 核、原形質流動の提唱
2.2.2.3.2. 余談
2.2.2.4. フィルヒョウ
2.2.2.4.1. 細胞は細胞からのみ生じる
2.2.2.4.2. 余談
2.2.3. 細胞の構成
2.2.3.1. 細胞
2.2.3.1.1. 後形質
2.2.3.1.2. 原形質
2.3. 生体を構成する成分
2.3.1. 元素比率
2.3.1.1. 人体だと
2.3.1.1.1. 重さランキング
2.3.1.1.2. ミイラの場合
2.3.2. 物質比率
2.3.2.1. どちらも水が多い
2.3.2.1.1. 水は比熱が高く、生体内の温度調整や物質輸送に役立つ
2.3.2.2. 人は水の次に**タンパク質・脂質**
2.3.2.3. 植物は水の次に**炭水化物**(細胞壁の構成成分がセルロース、つまり炭水化物)
2.3.2.3.1. タンパク質と炭水化物の違い
2.3.3. タンパク質
2.3.3.1. アミノ酸がいっぱい結合して意味を成したもののことを云う
2.3.3.2. アミノ酸
2.3.3.2.1. 構成要素
2.3.3.2.2. 結合
2.3.3.2.3. 著名なアミノ酸
2.3.3.3. タンパク質の多次構造(アミノ酸の集まりのさらに集まり)
2.3.3.3.1. 一次構造
2.3.3.3.2. 二次構造
2.3.3.3.3. 三次構造
2.3.3.3.4. 四次構造
3. 実験器具
3.1. 顕微鏡
3.1.1. 長さの単位
3.1.1.1. 小さい順
3.1.1.1.1. 1m
3.1.2. 分解能
3.1.2.1. どのくらいまでなら見えるかというもの
3.1.2.2. 肉眼
3.1.2.2.1. 0.1mm
3.1.2.3. 光学顕微鏡
3.1.2.3.1. o.2μm
3.1.2.4. 電子顕微鏡
3.1.2.4.1. o.2nm
3.1.3. 観察の仕方
3.1.3.1. ステップ1
3.1.3.1.1. 固定
3.1.3.2. ステップ2
3.1.3.2.1. 乖離
3.1.3.3. ステップ3
3.1.3.3.1. 染色
3.1.3.4. ステップ4
3.1.3.4.1. 押しつぶし
3.1.4. 見えるもの
3.1.4.1. 大きさ:うちら>**単細胞真核生物**>**多細胞真核生物の中身**>**原核生物**>>越えられない壁>>**非細胞成分**
3.1.4.2. 単細胞真核生物
3.1.4.2.1. ゾウリムシ
3.1.4.3. 多細胞真核生物の中身
3.1.4.3.1. ヒトの卵
3.1.4.3.2. 一般の細胞
3.1.4.3.3. 赤血球
3.1.4.4. 原核生物
3.1.4.4.1. 大腸菌
3.1.4.5. 非細胞成分
3.1.4.5.1. ウイルス
3.1.4.5.2. タンパク質
4. 異化
4.1. 生体内で起こる分解反応
4.1.1. 発酵
4.1.1.1. 脱水素酵素
4.1.1.2. ピルビン酸
4.1.2. 呼吸
4.1.2.1. ミトコンドリア
4.1.2.1.1. 解答系
4.1.2.1.2. クエン酸回路
4.1.2.1.3. 電子伝達系
4.1.2.2. 呼吸商
4.1.2.2.1. 使った酸素のうち、どのくらい二酸化炭素が出たかを呼吸商という
4.1.2.2.2. 排出した二酸化炭素÷摂取した酸素
4.1.2.2.3. 1以上:呼吸と発酵の併用
4.1.2.2.4. 1:炭水化物
4.1.2.2.5. 0.8:タンパク質
4.1.2.2.6. 0.7:脂肪
4.2. エネルギーを作る
4.3. ATP
4.3.1. ADP
4.3.2. アデノシン3リン酸
4.3.2.1. アデニン
4.3.2.2. リボース
4.3.2.3. リン酸
4.3.2.3.1. 高エネルギーリン酸結合
5. 同化
5.1. エネルギーを用いる
5.1.1. 炭酸同化
5.1.1.1. 光合成
5.1.1.1.1. 光合成色素
5.1.1.1.2. 葉緑体
5.1.1.1.3. 光合成のステップ
5.1.1.1.4. 光合成曲線
5.1.1.2. 細菌
5.1.1.2.1. 光合成細菌
5.1.1.2.2. 化学合成細菌
6. 器官
6.1. 神経
6.1.1. ニューロン
6.1.1.1. 樹状突起
6.1.1.1.1. 細胞体
6.1.2. シュワン細胞
6.1.2.1. 髄鞘(絶縁体)
6.1.2.1.1. 神経鞘
6.2. 効果器
6.2.1. 筋肉
6.2.1.1. 横紋筋
6.2.1.1.1. 骨格筋
6.2.1.1.2. 心筋
6.2.1.2. 平滑筋
6.2.1.2.1. 内臓筋
6.2.1.3. 筋肉の大きい順
6.2.1.3.1. 骨格筋
6.2.1.4. 筋収縮
6.2.1.4.1. 1.運動神経の末端からアセチルコリンが出、それを受け取った膜がカルシウムチャネルを開く
6.2.1.4.2. 2.カルシウムチャネルから出たカルシウムがトロポニンと結合し、アクチンフィラメントを動かす
6.2.1.4.3. 3.アクチンフィラメントがミオシンフィラメントを動かす
6.2.1.4.4. 刺激に対する筋肉の反応の仕方
6.2.1.4.5. 筋収縮のエネルギー
6.3. 受容器
6.3.1. 眼
6.4. 排出系
6.4.1. 腎臓
6.4.1.1. 尿のろ過、再吸収をするところ
6.4.1.2. あるもの
6.4.1.2.1. 重要
6.4.1.2.2. 若干重要
6.4.2. 尿形成
6.4.2.1. 腎単位
6.4.2.1.1. 尿を作る1セットのこと
7. 分類学
7.1. ドメイン
7.1.1. 界
7.1.1.1. 門
7.1.1.1.1. 網
7.1.2. ヒト
7.1.2.1. 真核生物ドメイン
7.1.2.1.1. 動物界
7.2. ドメイン
7.2.1. 細菌ドメイン
7.2.2. 古細菌ドメイン
7.2.3. 真核生物ドメイン
7.2.3.1. 酵母菌
7.3. 界
7.3.1. 五界説
7.3.1.1. 提唱:ホイッタカー
7.3.1.2. 改良:マーグリス
7.3.2. 原核生物界
7.3.2.1. 細菌
7.3.2.2. 古細菌
7.3.2.2.1. ドメインでは別なのに一緒
7.3.2.3. 原核生物のやつらがこれ
7.3.3. 原生生物界
7.3.3.1. 真核の単細胞等
7.3.3.2. 藻類
7.3.3.2.1. 植物に進化
7.3.3.3. 粘類
7.3.3.3.1. カビ、キノコに進化
7.3.3.4. 原生動物
7.3.3.4.1. 動物に進化
7.3.3.4.2. ミドリムシ等
7.3.4. 植物界
7.3.4.1. 水から遠のいていく
7.3.4.2. 緑藻
7.3.4.2.1. コケ植物(クチクラ獲得)
7.3.5. 菌界
7.3.5.1. キノコ、カビ
7.3.6. 動物界
7.3.6.1. 新口
7.3.6.1.1. 原口がお尻にない
7.3.6.2. 旧口
7.3.6.2.1. 原口がお尻にある
7.4. 原核生物と真核生物
7.4.1. 原核生物
7.4.1.1. 核膜なし
7.4.1.2. 膜構造未発達
7.4.2. 真核生物
7.4.2.1. 核膜あり
7.4.2.2. 膜構造発達
7.4.2.2.1. 膜を作ることで反応がしやすくなっている
7.4.2.3. 真核自体の進化の歴史
7.4.2.3.1. ステップ1
7.4.2.3.2. ステップ2
7.5. 単細胞生物・多細胞生物等
7.5.1. 単細胞生物
7.5.1.1. 単一の細胞、個体である生物
7.5.2. 多細胞生物
7.5.2.1. 多数の**分化**した細胞で個体が形成
7.5.3. 細胞群体
7.5.3.1. 多数の細胞はあるが、分化が乏しく
7.5.3.2. イメージ的には**ルームシェア**
7.5.3.3. 小さい順
7.5.3.3.1. クラミドモナス
