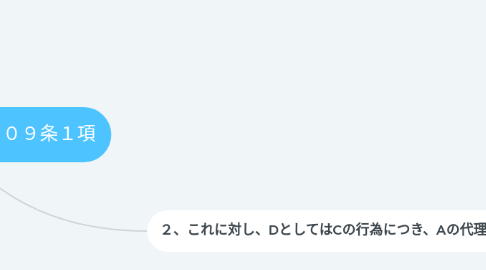
1. 1、AのDに対する所有権(206)に基づく物権的妨害請求権としてのD抵当権登記抹消手続請求の可否
1.1. ⑴①A所有②D抵当権登記が認められる必要があるが、これは認められる
1.2. ⑵これに対し、Dとしては登記保持権原として、Aの代理人CとDの抵当権設定契約の効果は本人Aに帰属すると主張
1.3. ⑶有権代理(99条1項)の成否。代理行為、顕名は認められる。
1.3.1. ア、代理行為に先立つ代理行為の授与
1.3.1.1. (ア)Dとしては本件白紙委任状交付をもって、授与成立主張
1.3.1.2. (イ)しかし本件では、AはそもそもCに交付してなく、Bに交付したのも、Bに代理権を与えるもので、不特定の者に代理権を与える主旨ではなかった(非輾転予定)
1.3.1.3. (ウ)よって、有権代理不成立。
1.3.2. イ、よって、無権代理。追認が必要(113条1項)
1.3.2.1. (ア)DはAの調査応諾をもって追認成立を主張
1.3.2.2. (イ)AはCからの融資のためと認識し調査に応じており、AD間においてもこの点の確認はされていない
1.3.2.2.1. よって、無権代理行為を追認したとはいえない
1.4. ⑷したがって、Aに効果帰属しないのが原則
2. 2、これに対し、DとしてはCの行為につき、Aの代理権授与表示による表見代理の成立を主張(109条1項本文)
2.1. ⑴要件
2.1.1. ア、無権代理行為、顕名あり
2.1.2. イ、無権代理に先立って、本人が「第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した」といえるか
2.1.2.1. (ア)「第三者」
2.1.2.1.1. 直接の相手方
2.1.2.1.2. Dは該当
2.1.2.2. (イ)AはBに白紙委任状を交付し、BはさらにCにこれを交付しており、Cは白紙委任状の転得者(非輾転予定型ー間接型)。Cはこれに自己の名前を記入しDに契約締結した
2.1.2.2.1. (ⅰ)転得者が白紙委任状を利用した場合の先立つ代理権授与表示の存否の判断基準
2.1.2.2.2. 非輾転の意図であれば、代理人名義を特定人とすることは容易であり、これを怠った場合は取引相手が信頼した場合の不利益は交付者が負うべき
2.1.2.2.3. 代理人名義白紙の場合、非輾転予定であっても委任事項の範囲内の行為であれば先立つ代理権授与表示があったものと考えるべき。
2.1.2.2.4. もっとも、委任事項の範囲外の行為が為された場合は、交付者の意図との乖離が激しいばかりでなく、相手方としても取引と委任事項の相違を委任状記載から把握できる
2.1.2.2.5. よって、この場合は先立つ代理権の授与はなかったものと考えるべき
2.1.2.2.6. そして、委任事項の範囲は相手方が把握できるかで画定すべき
2.1.2.2.7. よって、特段の事情がない限り、委任事項の範囲は委任状の記載を持って客観的に判断する
2.1.2.2.8. (ⅱ)本件では代理人名白紙である為、委任事項の代理権授与表示あり
2.1.2.2.9. 委任事項の範囲は「A所有不動産に対する抵当権設定に関する一切の件」
2.1.2.2.10. Cの無権代理はBでなく自己のためではあるものの抵当権設定登記
2.1.2.3. (ウ)したがって先立つ代理権授与表示あり
2.1.3. ウ、要件充足。表見代理は成立するように思える
2.2. ⑵これに対し、AはDの「過失」を主張(同但書)可否?
2.2.1. ア、「過失」の意義
2.2.1.1. 予見可能性に基づく結果回避義務違反
2.2.2. イ、AとCは全くの他人。2000万の高額な被担保債務。不動産という高価な目的物。
2.2.2.1. 不審事由あり、よって予見可能性あり。
2.2.2.1.1. これに基づき、Aの代理権授与が本当にあるかを慎重に確認すべき高度な確認義務。
2.2.3. 履行は容易。
2.2.3.1. 懈怠あり。
2.2.4. ウ、過失あり。Aの主張認められる。
