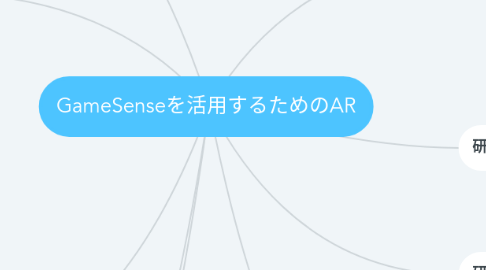
1. テーマの変更:FBの向上
2. 課題
2.1. 現時点でGameSenceができるかどうか
2.1.1. 色んな人から意見を貰う
2.1.2. メンバーが来年の6月で引退する
2.1.2.1. 逆算するともう一年ない
2.1.3. 女子も同じ状況
2.2. 現場のレベル
2.2.1. GameSenceを行うのに最低限の技術が何なのか。
2.2.2. 人数が少ない7,8人
2.2.2.1. 部員人数が減ったときどうするか
2.2.3. 男子女子の合同
2.2.3.1. 女子20人
2.2.4. 全員初心者
2.2.5. 練習時間90分、週3日
3. 研究目的
3.1. 自身のコーチングスキルを高めるため
3.1.1. どのようなコーチングスキル?
3.1.1.1. Questioning
3.1.1.1.1. 練習中
3.1.1.1.2. ミーティング
3.1.1.2. FB
3.1.1.2.1. 練習中
3.1.1.2.2. Timeout
3.1.1.3. 指示する
3.1.1.4. コンテキストを読み取る
3.1.2. 何をもってコーチングスキルが 上がったと言えるか。
3.1.2.1. GameSenseを行う過程で目的(答え)を コーチが言わなくとも理解している状態。
3.1.2.2. プレーヤー自身の思考を促し、目的にたどり着き、学習が存在する状態。
3.1.2.3. 適切なGameSenseをデザインし、 提供できているか。
3.2. GameSenseとは
3.2.1. ゲームを読み、適切なオフ・ザ・ボールの動きで対応し 、オン・ザ・ボールの時には適切な動きのレスポンスを実行する(プレーの文脈の中で成功する)
3.3. GameSenseの目的
3.3.1. ゲームで成功するために必要な戦略、スキル、ルールの理解を深めるように 選手に段階的に挑戦させ、動機づける練習をデザインすること。
4. 予測
4.1. GameSenseの重要性はもちろんのこと、同時にスキル練習も行うことが大事で偏ってはならない。
5. 社会的貢献
5.1. 国内のGameSenseに関する先行研究が少ないことから、積み重ねることへの一歩となる。
6. 背景
6.1. 指導者への不信感。 こんな指導者は嫌だ。
6.1.1. ドリルやゲームにおける説明不足 または、説明できないことをごまかす人。
6.1.1.1. 自分がそんな指導者にならないために、 コーチングスキルを高めたいと思った。
6.2. 目指すコーチング像 (なりたい自分)
6.2.1. 選⼿⾃⾝にゲームを通して学習があるかどうか(ドリルではなくゲーム中⼼練習構 成・ゲームの中でどんな制限を持たせるのか)
6.2.2. あらゆる疑問や質問を説明できること または一緒に考えられること。
6.2.3. アスリートの主体性を尊重
6.2.3.1. 民主的なコーチング
6.2.4. 自分自身も幸せであること
6.3. オープンスキル種目であるにも関わらず、練習ではドリル中心の練習が多く、 状況判断を伴う練習が少ないように思えた。スキルと状況判断の紐づけがされていない。
6.3.1. だから、常に状況判断の求められるゲームを中心としたGameSenseを活用できるようにしたい。
6.3.1.1. GemeSenseとドリル練習を適切に使い分ける
6.3.2. これに対する否定に対しての論文 例:私の経験の多くはドリル中心ではありませんでした。ちゃんと状況判断練習してました。
7. 研究内容
7.1. 研究対象を自分自身にして、コーチングスキルを高めることを目的としたAR
8. 研究方法
8.1. 計画
8.1.1. サイクル回数
8.1.1.1. 4回
8.2. 行動
8.2.1. プレ研究をいつするか
8.2.1.1. もう少しGameSenseを理解してから、なるべく早く2年になった頃には始めたい。
8.2.2. 録画、録音
8.2.2.1. 個人情報取り扱い承認手続き
8.3. 評価
8.3.1. 指導教諭とCF
8.4. 省察
8.4.1. 指導教諭とCF
