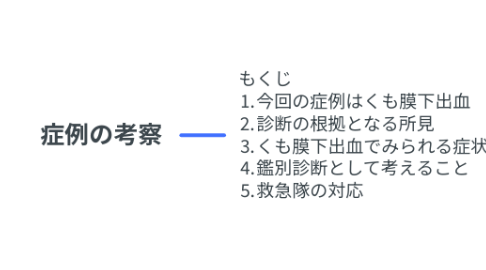
1. もくじ ⒈今回の症例はくも膜下出血 ⒉診断の根拠となる所見 ⒊くも膜下出血でみられる症状 ⒋鑑別診断として考えること ⒌救急隊の対応
1.1. ⒈今回の症例はくも膜下出血
1.1.1. 今回の症例はくも膜下出血でした。
1.1.1.1. くも膜下出血では様々な症状を発症します。
1.1.1.2. 私なりの考察も含めたので、参考にしてください。
1.2. 診断の根拠となる所見
1.2.1. ・突然発症した激しい頭痛
1.2.2. ・繰り返す激しい嘔吐
1.3. くも膜下出血でみられる症状
1.3.1. 典型的なのは「突然の激しい頭痛」
1.3.1.1. 頭痛の性状は「バットで殴られたような」と表現するような痛みが特徴です。
1.3.1.2. 頭痛と共に、嘔吐を繰り返します。
1.3.1.3. 「頭痛」+「激しい嘔吐」はキーワードです。
1.3.1.4. 「突然の激しい頭痛」は、髄液中へのわずか数mLの出血で引き起こされます。
1.3.1.5. この程度(数mL)の出血では脳圧は亢進しないし、脳ヘルニアも生じません。
1.3.2. くも膜下出血の局所神経症状
1.3.2.1. 片麻痺や瞳孔不同、共同偏視はなぜ出ない?
1.3.2.1.1. 出ない理由は、髄液中へわずかしか出血していないからです。
1.3.2.1.2. **もし、くも膜下出血に脳内血腫が合併すれば片麻痺や瞳孔不同、共同偏視などの局所神経症状は生じます。**
1.3.2.2. 出血量が多いと脳ヘルニアを発症
1.3.2.2.1. 出血量が著しく多量の場合は、脳圧亢進から脳ヘルニアを合併します。
1.3.2.2.2. この場合は、予後不良です。
1.3.3. 髄膜刺激症状
1.3.3.1. 髄膜刺激症状は「項部硬直」、「ケルニッヒ徴候」、「ブルジンスキー徴候」を指します。
1.3.3.2. 但し、陽性反応はすぐ出現しません。
1.3.3.2.1. 陽性となるまで数日を要するため、発症直後のくも膜下出血では陽性となりにくいです。
1.3.4. 神経原性肺水腫とたこつぼ型心筋症
1.3.4.1. くも膜下出血や脳出血による髄液内への出血、または頭蓋内圧亢進は、交感神経刺激を引き起こします。
1.3.4.2. 原因
1.3.4.2.1. ①延髄の循環中枢に対する(交感神経性の)直接刺激
1.3.4.2.2. ②髄液に流出した血液に含まれる炎症メディエーターの刺激
1.3.4.2.3. 上記2つが考えられます。
1.3.4.3. 神経原性肺水腫
1.3.4.3.1. 交感神経過緊張のため、血液内ノルアドレナリン濃度は著しく増加
1.3.4.4. たこつぼ型心筋症
1.3.4.4.1. 交感神経が活性化し血液中に大量のカテコラミン(アドレナリン、ノルアドレナリン)が放出されて心臓の筋肉が障害されるため引き起こされると考えられています。
1.4. 鑑別診断として考えること
1.4.1. 鑑別診断として考えられる疾患をピックアップします。
1.4.1.1. 但し、あくまで鑑別のためです。
1.4.1.2. **今回の指令内容からまず疑わなければならないのは「くも膜下出血」です。**
1.4.1.3. 大前提は、緊急性が高く、早期搬送が必要な疾患に目を向けておきましょう!
1.4.2. 頭痛
1.4.2.1. COMMON(頻度:高)
1.4.2.1.1. 外傷後頭痛
1.4.2.1.2. 全身性感染症に伴う頭痛
1.4.2.1.3. 緊張型頭痛
1.4.2.1.4. 急性副鼻腔炎
1.4.2.1.5. 高血圧性頭痛
1.4.2.2. LESS COMMON(頻度:中)
1.4.2.2.1. くも膜下出血
1.4.2.2.2. 脳出血
1.4.2.2.3. 片頭痛
1.4.3. 嘔吐
1.4.3.1. COMMON(頻度:高)
1.4.3.1.1. 小脳梗塞・出血
1.4.3.1.2. 心筋梗塞
1.4.3.1.3. 糖尿病性ケトアシドーシス(DKA)
1.4.3.1.4. 小脳閉塞(SBO)
1.4.3.1.5. 虫垂炎
1.4.3.1.6. 胆嚢・胆管炎
1.4.3.1.7. 膵炎
1.4.3.2. LESS COMMON(頻度:中)
1.4.3.2.1. 大動脈解離
1.4.3.2.2. 急性緑内障発作
1.4.3.2.3. 尿毒症
1.4.3.2.4. 細菌性腸炎
1.4.3.2.5. 低ナトリウム血症
1.4.3.2.6. 高カルシウム血症
1.4.4. などなど。
1.4.4.1. でも、こんなに多くの病態をあーでもない、こーでもないと考えていては、早期搬送はできません。
1.4.4.2. ある程度、的を絞ることが重要です。
1.4.4.3. 例えば、「突然発症した頭痛を訴え、激しく嘔吐している」
1.4.4.3.1. これならまず、くも膜下出血を疑う。
1.4.4.3.2. でも、他の疾患の可能性はないか神経所見を観察していく
1.4.4.3.3. 麻痺は出ていない
1.4.4.3.4. 心電図では、広範囲にST上昇を認める
1.4.4.3.5. くも膜下出血でも心電図変化は出るよな?
1.4.4.3.6. でも、確定診断までできないから、脳外科・循環器もみれる総合病院へ搬送しよう。
1.4.4.3.7. こういった感じです。
1.4.4.3.8. 同じ脳疾患を疑っているだけなら脳外科のある医療機関へ搬送で迷いませんが、脳外科と循環器科だと搬送先が大きく異なります。
1.4.4.3.9. ある程度、的を絞り、その上で搬送先を決めることが救急隊に求められます。
1.5. 救急隊の対応
1.5.1. 安静搬送を心がける
1.5.1.1. 目からの刺激(瞳孔観察省略)だけでなく、
1.5.1.2. 布担架などでストレッチャーまで移動する際にも注意が必要。
1.5.1.3. もし不用意に強い刺激を与えてしまうと、容態変化して予後を悪化させてしまいます。
1.5.2. 救急救命士の血糖測定
1.5.2.1. 救急救命士は、意識障害の傷病者に対して血糖測定を実施できます。
1.5.2.2. 但し、くも膜下出血を疑う傷病者には禁忌となっています。
1.5.2.2.1. 病院ではルーティンでやっているところもありますが…
1.5.2.3. 今回の症例はまさに”血糖測定やってはいけない”現場となります。
1.5.3. 搬送先医療機関の選定
1.5.3.1. 今回の症例はくも膜下出血です。
1.5.3.1.1. とりあえずの診断はついたものの、循環器疾患を疑わせる所見も認められます。
1.5.3.1.2. 私は、脳外科単科での搬送は躊躇してしまいます。
1.5.3.1.3. なぜなら、救急隊は確定診断できないからです。
1.5.3.1.4. 例えば、「突然発症した頭痛を訴え、激しく嘔吐している」
1.5.3.1.5. 例えであげたような思考を浮かべてしまいます。
1.5.3.1.6. ここでの答えは1つではありません。
1.5.3.1.7. 地域性もありますので、職場の上司や同僚と話し合ってみてほしいです。
