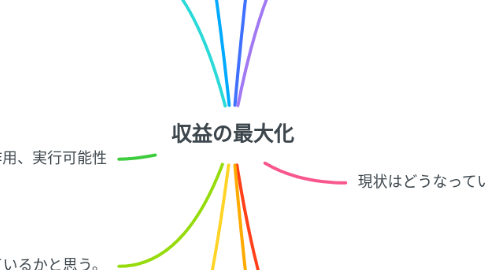
1. なぜ問題がおこったのか
1.1. 【福岡】資料の通り。
1.2. 【長崎】長崎は地理的要因で平野部が少なく、耕地が散在している。JAは一般客からは近寄りにくい。農薬系統メーカーは競合しており3社もいらないのでは。事務量の削減・合理化が必要。北部九州ができて減ったものもあるが、それ以外の事務量が増えているのでは。
1.2.1. 北興、協友は水稲剤しかない。クミカは園芸剤もあり戦える。
1.2.2. 【長崎】事務量の削減は農薬の場合は年間予約などがあげられる。事業所の事務も3県統一化ができるようシステム化できればよい。
1.3. 【大分】
2. どのような解決策があるのか
2.1. 【福岡】各県本部でよい取り組みをしているはず。それを共有しつつ実践ができればよい。
2.1.1. 中四国管内県本部との議論や先進県への共同視察など
2.2. 【長崎】分量と収益どちらも訴求しなくてはいけないのか。購買力の強化にはどうすればよいのか議論したい。
2.2.1. 【福岡】赤字でなければ分量。合併で見積合わせが増えている。受発注システムでJAの事務処理が楽になっており多少商系が安くても全農へ注文が来ることもある。園芸剤は「物流」業務で収益を確保。JAさがのような購買委員会方式でやってみたい。
2.2.1.1. アマゾンのようなEC化。コメリよりも多少安価な価格設定を全農主体(当用)で行いたい。予約はJAが価格を決定。そのためには肥薬以外の品目も取り組む必要がある。
2.2.2. 【長崎】県央は天秤購買をやっているが、その他は要領でなんとか分量を確保している。単品で入札が発生すると厳しい。
2.2.3. 【大分】大分は天秤購買というよりもJAへの経営支援を求められ、組合員に還元されない。分量がないと資金を作れない。収支の観点から事務要員を可能な限り削減できればよい。かつて検討していたが受発注機能を北部に集約するのも一案。
2.3. 【大分】
3. リスク・副作用、実行可能性
3.1. 【福岡】特に意見なし。
3.2. 【長崎】事業所への業務集約と県本部の推進特化。
3.3. 【大分】JAの機能回復が前提だが、現時点では判断できる状況ではない。
4. 【本間】暦の統一はすぐには難しいが、今後上市される剤は協議の上調整することは可能ではないか。大分はJAごとの対策が少ないので進めやすいが他県ではJA数も多いので難しいかもしれない。事業所では似たような覚書が多く統合した方がよいものがあると感じる。価格だけではなく、質も求められてくる。システム・物流もそれに含まれているかと思う。
5. その他
5.1. 【荒瀬】県本部だけだとメーカーと協議できないことも多い。3県で共通して事業者がまとめて協議してほしい。福岡は全JAで入札を実施しているため手間が多い。
5.1.1. 集約が可能な品目を選定して条件を厚くもらう。
5.2. 【田淵】肥料は事務が多いことに驚いた。肥料の主任者業務の軽減が必要では。商品のラインナップ的に商系の肥料を扱えず困ることも多い。商系銘柄を事業所で契約することも可能では。JAの機能が弱体化していると感じている。受発注システムを皮切りに生産者と直接取引を行う方向で検討すべき。
5.3. 【兼子】農薬の3県統一暦も提案できるのであれば提案してほしい。
5.4. 【石田】事務の統一化については具体的には思い浮かばないが、県域の推進力を上げる施策については賛成。システムを現状よりも強化してほしい。受託散布についてはドローンが流行し始めて分量が減少し始めた。肥料の事務については集中購買が一番手間だ。
5.5. 【岩井】3県本部で基準B価を統一できないか。現状実態は奨励金を織り込んでJAはA価を設定している。
5.5.1. 【長崎】長崎の場合は基準B価からA価を作成している。ネット市況で問題になっている品目以外のA価を全農が決めると問題になる。年度末のまとまった後戻しに期待しているJAが長崎の場合まだ多い。折込がよいとは言われるが・・・。JAがさらに分量を商系にとられると意識は変わるかもしれないが、その前にJAを説得すべきかもしれない。
5.5.2. 大分は説明すれば理解は得られるとは思うが、課題はいくつかあるはずなので整理させてほしい。
5.6. 【岩井】農薬系統メーカーの話があったが、彼らに配慮もしなくてはいけないとも考えている。例えばバラ返品の受付など系統メーカーに対応してもらっているものもある。彼らの推進力を借りていることも念頭に議論したい。
6. 何のために議論をするのか
6.1. 【福岡】共通点が多い農薬から検討ができればよい
6.2. 【大分】大分はJAの機能が低下している。店舗機能の強化を図っているが実績に結び付いていない。JAというよりも組合員からどう全農が選ばれるのかを検討すべき。
6.3. 【長崎】2030年までに田畑面積が減少するなかで防除受託まで受託できるような体制づくりの検討が必要。JAへ奨励処置を行ってきたが実績増加に結び付いていない。現状市況に振り回されており、価格によらない仕組みづくりが必要。
7. ありたい姿・あるべき姿
7.1. 【福岡】委託関係については営農開発部と検討している。JAみなみ筑後は受託散布をすでに実施しておりモデル化を検討している。3県本部で実施するのであればしっかりと検討する。定款の変更で全農自ら農業を行えるようになるのでモデル圃場を活用していく。受発注センターシステムを活用しながら、物流とシステムで一定程度稼ぐことができるのではないか。
7.1.1. 3~5人程度で農業経営をしながら情報発信を行うと面白いのでは。圃場さえあればいろいろなことができる。
7.1.1.1. 福岡のみでは難しいため、大分、長崎と一緒にできればと【本所営農部署より】
7.1.2. 福岡県本部長はいちご、ぶどうをイメージしている。肥薬ではヘリ防除と近い仕組みで進められれば。
7.1.3. ゆくゆくは全農自ら営農を
7.1.3.1. 福岡県南部は農薬散布は商系業者多い
7.1.4. 最近は防除受託そのものが減少している。生産者が高齢化し「営農委託」を希望しているのでは。
7.2. 【長崎】園芸・農産部門と連携を深めなくてはいけない。大規模法人対応については「担い手サポートセンター」が中央会内に設立されたのでこちらと連携する。
7.2.1. 担い手サポートセンターは設立されて間もないため手探り状況。大規模法人のリストアップから。対象は水稲、園芸、畜産
7.2.2. オーダーメードBBは最終目標。大規模生産者法人向けのBBを作りたいが、コストメリットを打ち出せてない。地域ブランドと強化ししっかりとした資材を使ってもらいたい。
7.3. 【大分】法人・大規模生産者にはすでにアプローチしている。「物売り」でよいのかという議論を進め、提案型の推進が必要ではないか。JAは地区本部単位で運送会社に委託しているが一部運送会社から撤退を打診されているため、県本部として受託も検討している。農機部門とドローンの受託業務を検討したこともあるがいまは止まっている。
8. 現状はどうなっているのか。何が問題なのか。
8.1. 【長崎】JAは人員募集をかけても集まらない。県本部職員の退職も0ではない。本所・県本部両方縦割りがあるためより横の連携を深めるべき。老朽化した施設の更新が必要。(県北センターはかなり古い)
8.1.1. 肥料主任の事務処理が多い。文書発信、価格作業、地区担当業務。
8.1.1.1. 人手不足でJA巡回業務を取りやめた。やらなくてもよい業務の取捨選択を。
8.1.1.1.1. 【大分】JAのTACがいなくなった際に業務が増えた。定期的ではなく、必要な時にしか生産者へ訪問できなくなった。システム化でだいぶ楽にはなったが。
8.1.1.1.2. 【福岡】昔のように残業ができなくなっている。若手も増えており教育にも手がかかっている。
8.2. 【福岡】久留米、八女地区で合併を検討している。これまでの手厚い推進よりも物流・システムで合理化しメリットをだすべき。
8.3. 【大分】JAの現場での推進力が落ちている。県本部でも属人的な仕事が増えており人事ローテーションを回せない。
9. 問題点を発見する切り口・視点
9.1. 【福岡】JA支援をこれから重視せざるを得ない。課長級が提案して新しいことを始めないと若手もついてこない。店舗関係など手間がかかるものは除外するのも考えている。一方JA-CATをやりたいと言っているJAもある。
9.1.1. 【長崎】JA西彼でもCATをいれたいと希望している。全農も小売りに携わってもよい段階に入っているかもしれない。
9.2. 【長崎】県内では一部JAしか導入できておらず効率化を実感できていない。全農取扱い品目すべてを入れないと導入しないと言っているJAもある。生産者の受発注までつなげないとコスト削減につながらない。(飼料、燃料等含む)
9.3. 【大分】肥料はこれという銘柄がない。農薬は市況に巻き込まれてしまう。システムは組合員発注システムを入れたが浸透していない。これ以上JAの弱体化がとまらなかったらJA業務の全農への移管も考えている。提案型の業務に移行しないと生き残れない。
9.3.1. 代金回収のみをJAの業務とする。
9.3.2. 受発注システムが普及していないのは部会員の反応が良くない。予約注文分を想定していたが、当用の需要が大きかった。
9.3.3. 【福岡】県内でも若手生産者が多いいちごで実施してみたいと考えている。
10. その中で何が問題か、その根拠は
10.1. 【福岡】資料の通り。
10.2. 【長崎】長崎の場合は肥薬ではなく、園芸部門が稼ぎ頭。肥薬の3倍ほど稼いでいる。それ以外が厳しいので逆に肥薬へのノルマになっている。
10.2.1. 部会の市場流通が主体で契約販売などはあまりやっていない。今後部会が弱体化する中で法人対応は考えなくてはいけない。
