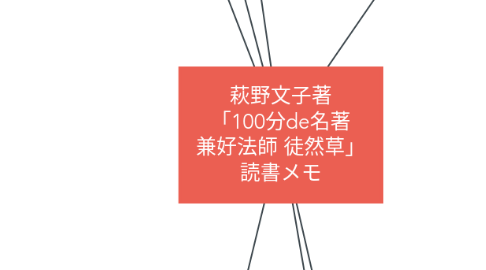
1. 世間を見抜け
1.1. 兼好が考える嘘つき
1.1.1. ばれるのもかまわず、口から出まかせを いい散らしている無邪気な嘘つき
1.1.2. 人から聞いたホラ話を、鼻をぴくぴくさ せて得意げに語る嘘つき
1.1.3. もっともらしい態度で、ところどころを ぼかしながら、よくは知らないふりをし て、それでいて辻褄を合わせて話を作る 嘘つき
1.1.3.1. 罪のある怖いタイプ
1.1.3.2. マルチ商法などの詐欺に多い手口
1.2. 兼好が考える 嘘に出合った時の反応
1.2.1. 言われるままに素直に騙される人
1.2.2. 嘘を信じ込み、さらに自分で意識的に 嘘の上塗りをして周囲に広めていく人
1.2.3. 右から左に流して、気にも留めない人
1.2.4. 信じるでもなく、かといって信じないで もなく、考え込む人
1.2.5. 本当だとは思わないが、そういうことも あるかもしれないと思って放っておく人
1.2.6. 相槌を打ち、微笑みながら、分かった様 子で聞いているけれども、実は何も分か っていない人
1.2.7. 本当かなと疑いながら、自分のほうが 間違っているのかなと悩む人
1.2.8. 嘘であろうが本当であろうが、かまわず に笑って楽しんでいる人
1.2.9. 嘘であることはお見通しだが、知らぬふり で黙っている人
1.2.10. その人がなぜ嘘をついているのかとい噓 の本意を理解して、協力して話を合わせ てあげる人
1.3. 教訓
1.3.1. おもしろおかしい話はたいてい愚かな人 間の作り事で、賢い人はそもそも大げさ な話はしない
1.3.2. 世間一般に常識として信じられているこ とを鵜吞みにせず、全方位から検証せよ
1.3.3. 人のことを嘲笑っていないで自分の足元 を見よ
1.3.4. 自分をいろいろな方向から眺め、つねに 自省を怠らないこと
2. 人生を楽しむために
2.1. この世に確かなこ とは何ひとつない
2.1.1. 人間はそのことに気づ かないまま生きている
2.1.1.1. しかし、気づかないからこそ 幸せに生きることができる
2.1.1.1.1. もしそれを心底悟ってしまったら、人生 の空しさに耐えかねて、生きることが難 しくなってしまう
3. 人を生きやすくする 無常という価値観
3.1. 兼好は、後二条天皇の皇太子である 邦良親王の家庭教師にだった
3.1.1. 邦良秦王が立派な天皇となるために、帝の心得や 有職故実を教えるためのテキストとして書き始め たのが「徒然草」
3.1.1.1. 有職故実とは: 朝廷や公家、武家の行事や法令、制度、 風俗、習慣、官職、儀式、装束などのこと
3.1.1.2. 途中で、邦良親王が 亡くなってしまった
3.1.1.2.1. 第39段あたりから、思うまま、 自在に書くようになった
3.2. 人生を楽しむためのコツ
3.2.1. 時には、一人の時間を過ごす
3.2.2. 優しい目線
3.2.3. 楽しむ
3.3. 嵐山光三郎の「徒然草」 から教えられたこと
3.3.1. この世は無常であり、だからそのことを しかと自分に言い聞かせて、ゆっくりと 急ぐのだ
4. 本文中に引用された段
4.1. 序段
4.1.1. つれづれなるままに
4.2. 第3段
4.2.1. 万にいみじくとも
4.3. 第5弾
4.3.1. 不幸に愁に沈める人の
4.4. 第6弾
4.4.1. わが身のやんごとなからむにも
4.5. 第7段
4.5.1. あだし野の露きゆる時なく
4.6. 第8段
4.6.1. 世の人の心まどはすこと
4.7. 第26段
4.7.1. 風も吹きあへず
4.8. 第37段
4.8.1. 朝夕へだてなくなれたる人の
4.9. 第38段
4.9.1. 名利につかはれて
4.10. 第41段
4.10.1. 五月五日、賀茂の競馬を
4.11. 第45段
4.11.1. 公世の二位の兄に
4.12. 第50段
4.12.1. 応長の頃、伊勢の国より
4.13. 第52段
4.13.1. 仁和寺にある法師
4.14. 第53段
4.14.1. これも仁和寺の法師
4.15. 第58段
4.15.1. 道心あれば
4.16. 第59段
4.16.1. 大事を思ひ立たむ人は
4.17. 第73段
4.17.1. 世に語り伝ふること
4.18. 第74段
4.18.1. 蟻のごとくにあつまりて
4.19. 第75段
4.19.1. つれづれわぶる人は
4.20. 第79段
4.20.1. 何事も入り立たぬ
4.21. 第80段
4.21.1. 人ごとに、我が身にうときこと
4.22. 第85段
4.22.1. 人の心すなほならねば
4.23. 第89段
4.23.1. 奥山に猫またといふものありて
4.24. 第92段
4.24.1. 或る人、弓射ることをならふに
4.25. 第107段
4.25.1. 女の物いひかけたる返事
4.26. 第108段
4.26.1. 寸陰をしむ人なし
4.27. 第109段
4.27.1. 高名の木のぼり
4.28. 第110段
4.28.1. 双六の上手
4.29. 第111段
4.29.1. 囲碁、双六好みて
4.30. 第116段
4.30.1. 寺院の号
4.31. 第123段
4.31.1. 無益のことをなして
4.32. 第126段
4.32.1. ばくちの負きはまりて
4.33. 第137段
4.33.1. 花はさかりに
4.34. 第142段
4.34.1. 心なしと見ゆる者も
4.35. 第150段
4.35.1. 能をつかむとする人
4.36. 第157段
4.36.1. 筆をとれば物書かれ
4.37. 第164段
4.37.1. 世の人あひあふ時
4.38. 第165段
4.38.1. あづまの人の
4.39. 第167段
4.39.1. 一道に携はる人
4.40. 第168段
4.40.1. 年老いたる人の
4.41. 第170段
4.41.1. さしたることなくて
4.42. 第172段
4.42.1. 若き時は
4.43. 第185段
4.43.1. 城陸奥守泰盛は
4.44. 第187段
4.44.1. 万の道の人
4.45. 第188段
4.45.1. 或る者、子を法師になして
4.46. 第190段
4.46.1. 妻といふものこそ
4.47. 第194段
4.47.1. 達人の人を見る眼は
4.48. 第211段
4.48.1. 万の事は頼むべからず
4.49. 第236段
4.49.1. 丹波に出雲といふ所あり
5. 心地よい人つきあいとは
5.1. その人の人間関係を見れば、その人 となりや価値観がよく分かるもの
5.1.1. 兼好法師の お友達になりたくない人
5.1.1.1. 身分の高い人
5.1.1.2. 若い人
5.1.1.3. 無病で身体の強い人
5.1.1.4. 酒を飲む人
5.1.1.5. 勇猛な武士
5.1.1.6. 嘘をつく人
5.1.1.7. 欲深い人
5.1.2. 兼好法師の つきあいたい人
5.1.2.1. 貢いでくれる人
5.1.2.2. 医者
5.1.2.3. 知恵を授けてくれる人
5.1.3. つきあうのならば、自分と似た価値観の人。風流なことでも、俗世のつまらぬこと でも、腹蔵なく語り合って、心が慰むのがうれしい。
5.1.4. 必ずしも意見が一致しなくともよい、食い違うところがあってもよい、むしろ大 事なのは「自分はそうは思わない」などと反対意見も遠慮なくいい合えること
5.1.4.1. これらのことから、自己中心的で相手へのこまやかな配慮に 欠けるタイプを嫌ったのではないか
5.2. 兼好法師
5.2.1. 生没年
5.2.1.1. 正確には分かっていないが、 1283年頃~1352年以降
5.2.1.1.1. 鎌倉時代末期~南北朝混乱期
5.2.2. 本名
5.2.2.1. 卜部兼好(うらべかねよし)
5.2.3. 元の身分
5.2.3.1. 下級貴族
5.2.4. 元の仕事
5.2.4.1. 20代で宮中に入り、後二条(ごにじょう)天皇に仕えた。事務職員にあたる 蔵人(くろうど)や、警察官にあたる佐兵衛佐(さひょうえのすけ)などを務めた
5.2.5. 男女観
5.2.5.1. 何だかんだといっても、男は女に血迷ってしまうもので、世間に非難されよう が、親に意見されようが、女を自分のものにしたい一心で悶々としてしまう。だ から、女は始末が悪い。
5.2.5.2. 筋金入りの独身主義者
5.2.5.3. 人間関係というもの全般に、深い情愛と 高い理想をもっていた人
5.2.5.3.1. 愛に対して純粋な人
5.2.6. 出家
5.2.6.1. 30歳頃
5.2.6.2. 理由
5.2.6.2.1. 不明
5.2.7. 和歌
5.2.7.1. 38歳の時に「続千載(しょくせんざい)和歌 集」に一首だけ入選
5.2.7.1.1. 「和歌四天王」の一人と称された
5.2.8. 「徒然草」を書いた
5.2.8.1. 48歳頃
5.2.9. 晩年は、「古今集」や「源氏物語」などの書写や校正をしたり、和歌や恋文の代筆などの アルバイトをしながら、70歳頃まで生きた
5.2.10. 特徴
5.2.10.1. いろいろな世界を渡り歩いたぶんだけ見分が広い
5.2.10.2. 物事を突き詰めて考える完全主義者
5.2.10.3. 人間くさく、まわりの人への深い興味を抱き続けた人間好きな人
5.2.10.4. 過剰なくらい中庸であることに心を砕いていた
5.2.10.5. 万事において玄人好み
5.2.10.5.1. プロフェッショナルな精神をよしとした
5.3. 「徒然草」の特徴
5.3.1. 先行きのわからぬ世であるからこそ、何も頼みにせず、自分は自分の価値観を貫 いて生きていこう、そんな割り切った軽やかさのある書物
5.3.2. 底流を貫くのは「この世に常なるものはない」という無常観
6. 上達の極意
6.1. 兼好が達人らから学んだこと
6.1.1. 油断大敵
6.1.2. 一意専心
6.1.3. 勝つ戦ではなく、負けない戦をせよ
6.1.4. 引き際が肝心
6.1.5. 用心には用心を重ねよ
6.2. 兼好が主張している上達の極意
6.2.1. 優先順位をつけよ
6.2.2. 恥を捨て人前に出よ
6.2.3. 真似でも行動せよ
6.2.4. 環境を整えよ
