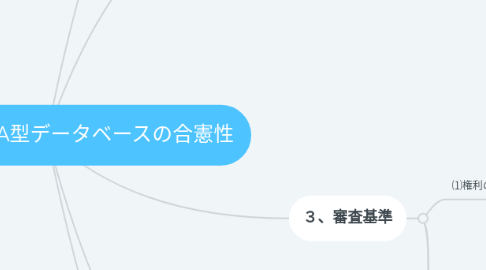
1. 1、助言の趣旨
2. 2、憲法上の問題の有無
2.1. ⑴Xの被疑者DNA型データベースに自己の記録をされない自由
2.1.1. 憲法13条は国民の私生活上の自由が公権力の行使に対しても保護されることを規定
2.1.1.1. 少なくとも個人情報が濫りに第三者に開示・公表されない自由は同条で保障される
2.2. ⑵
2.2.1. しかし、本件データベースへの記録は収集された個人情報の利用・管理に過ぎない
2.2.1.1. ア、個人情報の利用・管理は前記自由を制約すると言えるか
2.2.1.2. イ
2.2.1.2.1. 利用・管理は開示・公表そのものではない
2.2.1.2.2. しかし、利用・管理の方法によっては収集された個人情報が流出し、開示・公表と同じ結果をもたらす可能性はある
2.2.1.3. ウ、本件データベースは法律では規則のみによっている
2.2.1.3.1. 法制度は国会などの厳しい審議を経ておらず、不備がありうる
2.2.2. よって、前記自由が制約される可能性がある
2.3. ⑶憲法上の権利の制約があり、その違憲性は審査されるべき
3. 3、審査基準
3.1. ⑴権利の重要性
3.1.1. ア
3.1.1.1. DNA情報の性質
3.1.1.1.1. 個人の道徳的自律に直接関わらない
3.1.1.1.2. しかし、住所・氏名などといった個人識別情報と違って、通常は収集すらされない情報であり、一定の範囲で公開が予定されるものではない
3.1.1.1.3. また
3.1.1.2. そして、高度に情報化した現代においては、プライバシー外延情報といえども検索や他の情報との結合によって、重大な意味を持ちうる
3.1.1.3. DNA情報はプライバシー外延情報の中で最も要保護性が高いものと言える
3.1.2. イ、よって、DNA情報を濫りに公表・開示されない自由は重要といえる
3.1.3. ウ、もっともこのような権利も「公共の福祉」に照らして一定の制限は予定されるものと考える
3.2. ⑵制約態様
3.2.1. そして、DNA情報が第三者に濫りに開示・公表されないような仕組みが確立していない以上、その開示・公表の危険は単なる抽象的な危険ということはできない
3.2.1.1. よって、その制約は一定程度認められる
3.3. ⑶審査基準
3.3.1. 中間審査
3.3.1.1. 目的が重要で、手段と目的の間に実質的関連性があれば合憲
4. 4、個別具体的検討
4.1. 目的
4.1.1. 目的は重要
4.2. 実質的関連性
4.2.1. 目的適合性あり
4.2.2. 必要かつ相当
4.2.2.1. 犯罪捜査の一環として保存自体は必要であった
4.2.2.2. 嫌疑は晴れているのであるなら、現時点で保存する相当性なし
